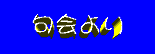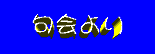秋
あざ蓉子
- 十月の海岸へゆく紙袋
- 支流が本流となり海岸へ。紙袋が一つ浮いている。これもいずれは、海へでるのだろうか。
よりどころがない。人もつきつめればみな一人旅。
前句もそうであったように、作者のみつめる目は、深く冷静だ。
あざ蓉子といえば、はなやかな赤というイメージで、春と夏に佳句が多いが私は冬の句が好きだ。
団塊の世代で、一時代を築こうともがき苦しんだ女の、ふっと気息を解いた瞬間の素顔が、秋冬の句にほの見える。
燃え上がる炎の中に透明な場所がある。(猿楽)
- (H13年11月20日)松永典子
大倉郁子
- 猿怖し居らねば淋し紅葉山
- 大阪箕面の猿は今では人に危害を加えるくらいの勢いで食べ物をねだってくる。安易に餌を与えたり、
山の乱開発で滝を枯らして人工的に自然をいじった結果、山の獣の餌が無くなって…と、人間の勝手さもその要
因の一つであるが、昔は愛らしかった猿の怖さが目立つようになった。怖いけれど居ないと淋しいというのも
人間の勝手な感情かもしれない。作者にはそれがよくわかっているのだ。存在の不安を感じる鋭敏な感覚と
坪内稔典氏に評され、さらに多彩に展開するに違いないと期待されていた作家であった。
- 行く秋や羽なきものは砂利踏んで
- 第一句集上梓後しばらくたったある日、電話を頂いた。このままでは感覚が鈍りそうだから一緒に句会を
したいから、紹介してくれという。虚名より本物の力を付けたいのだと。十分な力が有るからこその内観と、頭の
下がる思いだった。
その後、夫君が亡くなり、一人暮らしのための家を見つけて引っ越しをされて
やれやれこれからという時の突然の訃報。無理をなさっていたのではと、心が痛む。未来図同人からの転身だった。
「ふくよかな手紙一通春の雨」 「地下室の独活育ちをり修二の忌」 「パン焦がし窓いつぱいの蝉の声」
「枕木を越えようとする冬の草」
「この着物一度着たきりシクラメン」
(遺句集「ふくよかな手紙」平成22年10月創風社出版)
- (H22年9月28日)松永 典子
今瀬剛一
- とび火して空へつづけり曼珠沙華
- あっという間に咲きひろがってゆく曼珠沙華。気が付いた時には辺り一面、緋縮緬の反物を流したように群れている。
その様子を作者はうつくしいとび火のようだと捉えた。地平線まで、あるいは山の端の空までつづくところまでか。やがて夕映えの刻。空の澄んだ夕焼けにまで火が移っていったというのだ。美しき大景である。人間のどうしようもなく無力なこと、悲しさ、美しさ、生存の不安、そしてそれ故に明日に続く希望、なども行間から立ち上ってくる。正攻法の平明さによる詩的空間の広やかな事。
- 蓮掘って家までをしたたりゆくか
- 蓮根堀りの実態に思いを巡らせた。今では流通の発達故に簡単に食卓に登る蓮根であっても、生業にしている者の苦労に対する感謝と労働への共感とをやや字余りでとつとつと表現した。労働とは手を汚す事、己自信がしたたる事なのだと。
初学の頃、子育てで手いっぱいだった私は、今瀬氏が指導された青年作家の句会への欠席投句で勉強させてもらった。月一回しか出られなかったので、地元支部に出席して、あとは東京句会とこの句会その他には、郵便か知り合いに持って行ってもらった。この句会へは、鎌倉佐弓氏に頼んでいた。佐弓さんの機知に飛んだ軽妙な返送文が楽しみだったのと、その頃の何にも知らないくせに(知らなかったからこそ)生意気だった私には丁度いい試練の場でもあった。
そんなこんなで、あこがれの大変な詩人に、厳しくもあたたかい評をいただいた。もう少し真剣に勉強しておくんだったと今でも悔やんでいる。
「沖へ行く船に日がさすふところ手」「どこへ倒れても月見草つかめさう」「ぞろぞろと枯木したがへ喪の帰り」「流燈を置く水底に石動く」「きき酒や喉をころがる星の数」(週末)
- (H15年10月7日)松永 典子
岩津厚子
- 玉虫のブリキのごとき死なりけり
- 玉虫は周知のとおり、玉虫の厨子の透彫の金具の下に張られたほどの美しい羽を持つ甲虫。
その金緑色、金紫色の縞の装飾は飛鳥人のあこがれでもあったのだろう。この世のものとも思えない
ような美しいものにも死は必ずやってくる。魂のぬけた紡錘型のそれは、それなりに美しくはあるが、
金属性のただの物になってしまったのだ。それをブリキのようだと、捉えた。
- 片つぱしから黄落の椅子たたむ
- 秋には戸外での催しも多い。学校行事でもあるのだろうか、滞りなくイベントも無事に済み、
世話役の何人かでたくさんのパイプ椅子をたたんでいるのだ。周りの並木道はおりしも銀杏などの
黄落が始まっていて、盛んに光を散らしている。静かで、一読して、情景が目に浮かぶ。
俳句形式
に、絶大の信頼をおいて、とても謙虚に研鑚を積んでいる。「沖」大阪支部と、「南風」は毎月太融寺で、
句会を開いていたので、もしかしたら、若き日の厚子さんとも廊下ですれ違ったかもしれない。俳縁の
不思議さを思う。
俳人協会幹事。「南風」同人、編集長。「子午線」代表。
「靴下を引つ張つてはく柿の花」
「秋出水みなばらばらのことを言ひ」「青空にさはつてゐたる朴の花」「腹筋を鍛へ女の夏来る」
「西瓜冷やしてミロ展へ出かけたる」「そこまでの距離にずぶぬれ西東忌」「手拭を首より抜いて祭鱧」
「寒明けの厩舎にかかる守り札」「雪だるま溶けても立つてゐるつもり」
(第二句集「快晴」平成18年7月角川書店)
- (H18年7月31日)松永 典子
梅村すみを
- 月の出を水の大津に待ちゐたる
- 大津は、いろいろな詩歌の題材になっていて、地名のよろしさが、古格と大人の句柄に寄与していて、うまくはまり込む。水の大津とは当り前のようでいてなかなか言えないものだ。
月の出と水とはよくあることだけれど、それが大津であるという感懐。挨拶。私は、地名には歴史やら、その地の人々の思いやらが、凝縮されて有るべくして有るのだと思っているので、昨今の地名変更やら、町村合併やらで消えてゆく名前が、いとおしい。それによっての便利さが、どれほどの事かと思う。失業率の高さと人手を減らす事への大いなる矛盾。あえて不便を選択する勇気ある決断で、目先の得を取る事よりも大事な、時代の損失を食い止めるという賢明な選択が出来ると思うのだが。
(冬麗)
- (H14年8月25日)松永 典子
遠藤若狭男
- 火だるまの声なき声の案山子かな
- 最近は妙にリアルなマネキンやらユニークな空き缶製、ペットボトルのエコもの、凝ったロボット
、完璧を期すテグスや霞み網でそんなものには頼らないという畑もある。昔の藁製のいかにもといったも
のはもうあまりお目に掛からなくなった。それでも童話の中やわれわれの貧しかった頃の心の風景として
はっきりと残っている。烏がばかにして頭に止まっていたり、それでもそれなりの役に立っていたのだろ
う。刈り入れがすんで用がなくなったら、藁くずと一緒に燃やされた。もともと人の形をしているので、
ある種のロマン的イロニーを想起するのだ。火だるまという言葉をうまく使って人間の底知れぬ不安など
を隠喩あるいは換喩として技巧を凝らしている。
- 旅鞄濡らして若狭しぐれかな
- 旅に出るところか、帰ってきたら若狭はしぐれていたのか、あるいは近場のちょっとした旅
だったのか、いずれにしろ降ったりやんだりの時雨。もともと「過ぐる」から出た言葉、本格的な冬に
なる前の日本海沿岸のほんの短い季節を情感を込めて若狭しぐれと呼んだ。本人が雨男と呼ばれていたの
かも知れない。読み手の想像力を掻き立てるための小道具の使い方が実に巧みだ。
福井県生まれ。もともと小説を志していたらしい。「狩」同人。実作者としての評論も鋭い。
「破蓮の裏も表もなく破れ」「芒野の風芒野を抜けられず」「廃船の中なる潮も秋きざす」
「海荒れて能登金剛の春いづこ」「飽食のあと白鳥の羽づくろひ」「たちまちに北山杉の雪景色」
「ナプキンに口紅のあと聖夜餐」「木のぼりをせし木を仰ぎ卒業す」「また父があと戻りして絵双六」
「昨日より水の濁りて蓮の花」(神話)
- (H17年9月14日)松永 典子
大島雄作
- 素振りバットの鶏頭に届きさう
- 一読して光景が目に浮かぶ。少年の素振りを離れた所から見ているのだ。
あるいは、本人の少年時代の一場面かもしれない。
秋の日差しの中。鶏頭が咲いている。そのすれすれのところをバットがひゅうと横切る。何度も何度も。
もしかしたらバットと鶏頭の位置は違うのかもしれないが、ここから見ていると届きそうなのだ。
まるでそれが標的であるかのように。静謐な情感が漂う。(青垣)
- (H13年10月29日)松永典子
大野崇文
- 空仰ぐことなく芦を刈り進む
- 昔の湖沼には必ずと言っていいほど芦原があった。芦、葦、葭。表記も多数。葭簀や簾、
屋根などに加工され、それだけ暮しに密着した植物だった。
万葉集にも多数取上げられる。
枕詞としては、ふる、ほか、間近し、吉野等にかかる「葦垣の」や、難波にかかる「葦が散る」や、
枕、足にかかる、「葦牙(あしかび)の」等これも多数。石川郎女が、大伴田主の足の病を見舞い、歌を
贈ったのが「吾が聴きし耳によく似る葦の末(うれ)の足ひく我が背つとめ給(た)ぶべし」「葦垣の中の
和草(にこぐさ)にこやかに我れと笑まして人に知らゆな」。その他、葦をふくむ雁(准南子)の故事。秋に
咥えてくる木が春に残っていたらそれは日本で死んだ雁のものとする俗信から外ヶ浜(青森)で雁を供養して
、雁風呂とか雁供養と称した風習があった。芦刈は一昔前までは晩秋の風物詩だったが、春の
葦焼きと共に今は身近ではなくなった。(空を仰ぐことなく)の重労働が当たり前の事だった。
- 雪渓を隠さむと霧かけのぼる
- 温暖化の影響で雪渓さえも減りつつあるという。人の滅多に来ない絶景として、晴れた日には仰ぎ見る
事ができるのが、霧が出てあたかも何かの意志のように、隠そうとしているのだ。大景は素直に詠めば心地
よい。
「狩」同人。
「風神の掻き分けて来る芒原」
「待つ事が罰かも知れず蟻地獄」「蟷螂の祈りのさまに枯れにけり」「食べるときみな狐がほ衣被」
「妻ありて子あり我あり冷奴」「仲なほりへのきつかけは大嚔」「吊るされてより鮟鱇の面がまへ」
「顔上ぐるたび母さがし汐干狩り」「あやしげな糸を垂らして浦島草」(第一句集「桜炭」平成3年2月牧羊社)
- (H18年10月1日)松永 典子
大牧 広
- 台風のちかづく父の大きくなる
- 今でも台風は多大な犠牲を残して去る。この時の作者は父をすでに亡くされている。おそらく少年の頃の、台風接近の状況であろう。
戦後のまだ木の家に大家族が住んでいた日本である。台風が接近すると父は屋根に登ったり雨戸を打ち付けたり垣根を直したりと、急にしゃきっとして大忙し。少し風も出てきたし、今のうちに出来る事をすべてやって不安がる家族を安心させなければ。そんな中子供達はいつもと違う状況に大はしゃぎ。余計な事をして父に叱られる。父を中心に家族が一つにまとまった自然との戦いに父の存在が大きく見えた事など、郷愁の一場面にちがいない。
- 深酔の寂鮎までは覚えをり
- 産卵のため下流に下る鮎。落鮎ともいう。下り簗などで捕る。
何かの集まりで、二次会三次会と呑みまわっているうちに朦朧としてあまり覚えていないままちゃんと家には帰りついていて、お約束の二日酔。たしかあの店で寂鮎が出たよなと。
酒で亡くなったようなもんだとの父への思いが重なり、自分もその齢に近づくにつれ父の気持や立場がより理解できるようになった。句集名も「父寂び」。男としての父に対する反発や共感をもってこの一書が成ったような気がする。初心の頃毎月東京句会にも句を出すようになって、七、八十人も参加するような大句会に常に高点をとる先輩のうちの一人だった。父だけでなく、家族に対するほんわかした思いの句が好評だった。
「端居してときどき妻の話聞く」「目を剥いて案山子同齢かもしれず」「鵙の贄見てより鵙が好きになる」「茗荷竹日曜のたび家を捨つ」「籐椅子に海を見てゐるとき敗けし」(父寂び)
- (H15年8月20日)松永 典子
北村仁子
- 葭の節粉ふいてゐる空浮巣
- 浮巣は鳰の巣で、水が増えたら浮いている。葭の間から見える子育ての様子はとても微笑ましいが、
巣立ちをした後の空になった巣はしんと淋しいものだ。元来そこらにあるもので作られているので、自然に還るも
のばかりでできていて、解体も自然にできていた。それが派手なひもやビニールが混じるようになってゴミにしか見え
ない事もある。この浮巣はまだ広い所のものだろう。浮巣を見ていたら葭の節が粉をふいているのを発見した。
- 流れまかせに四万六千日詣
- 7月9、10日の両日、東京浅草寺の境内に鬼灯市が立つ。10日に詣でると普通の日の四万六千日分詣でた事に
なるという。随分と横着で都合のいい話ではあるが、信じる事が善男善女たる資格であるようである。ホウズキ市に来た
もののごった返しの人波に流されて付いてゆくと今日は四万六千日だった。自分もついで参りをしたというのだ。
実力者であった。「紫蘇つぼの思いつめたる色となる」とか「髻のはらりと解けし曼珠沙華」などすらりと詠んで、見え
ないところにも細心の神経を行き届かせる。70~80人の句会から20人ほどの小句会でもいつも高点句を独り占めにしてい
た。熱心で勉強家で短期間でうまくなった人であった。それだけに旨すぎて本人の個性が見えない、誰かの発想にあると
の批判も受けていたようだ。しかし俳句はまづ、うまくなければならないと、初心の頃の私は今は亡きこの先輩にあこ
がれてもいた。
「葺替の木釘こぼるる荒筵」 「さう言えば迎火どきの猫を見ず」 「山痩せのはじめは桐の一葉より」
「撒餌して鳰にいくらか依怙贔屓」
「棒立ちのものばかりなり火事の跡」 「死が葬にすばやく変る春障子」
「意趣返しされたる毛虫かぶれなり」 「日ざしよりぬくき落穂のひとにぎり」 「立冬のとろ火強火の鍋二つ」
「新入りは楽譜の読める祭笛」 「煤逃げの床屋にしては長かりし」「恋終りてもときをりの通ひ猫」
(第三句集「木沓」平成3年富士見書房)
- (H22年7月17日)松永 典子
神戸周子
- 電球のちちちちと鳴く秋はじめ
- ちょっと昔の電球の感じである。今はLEDという憎らしい程長持ちする電球にとって代わられる勢いだが、
それはそれで趣があるのだろう。その時代がわかるという事も俳句のよさの一つではないだろうか。切れかかった
電球は息もきれぎれのような音を立てる事がよくある。物も人もその時代に確かに共存していた。俳句は生きている
という共感である。人も動物も木も月も星も物質も、お互いを介して生存を確かめる。秋はじめは淋しさを意識する
季節はじめでもある。
- だんだんに月に近づく踊かな
- 「沖」に入る前に2年ほど添削指導を受けていたから私の最初の師でもある鈴木鷹夫の元で活躍中。相当な
勉強家であると聞く。ほぼ30年の句歴は伊達ではなく、鷹夫のうまさをしっかりと受け継いだようだ。帯文も手放し
の褒めようである。もっとも実力者を大勢排出した結社は句会ではとても厳しく、うまくても点の入り易い句ばかり狙って
いても、しっかりとダメ出しが入るし、逆選なども句会で言い合うものであって、句集を出してからではない。句集に
出すからには捨てる句は捨て去って主宰の目の篩を何度も通り抜けた句のみを上梓するもので、誤字がある句集なんて、
もっての外。平気で出す出版社も信じられないけれど、出版不況といものはそういう安易さが引き起こした現象であると
思う。決して不況のせいでもなく、電子書籍の台頭のせいでもない。そんな普段の厳しさを通ってきたからこその選者の
喜びでもあるだろう。
「こともなげに母の逝きしよ百千鳥」 「小突かれてはんざき一年分動く」 「ゆく水に月の乗りけり西行忌」
「シシ・カバブ蠍も食べて聖五月」
「ひと筋の冷気となりて鬼やんま」 「芋虫のそろそろ発酵する頃か」
「ぽつぺんのいたいけな音転がりぬ」 「鮟鱇のどの部分やら買いにけり」 「落ちてより完璧となる椿かな」
「春風やゆらゆら象の尻三つ」 「鵙高音誰かが嘘をついてゐる」
(第三句集「展翅」平成22年7月ふらんす堂)
- (H22年7月30日)松永 典子
小池万里子
- 流灯のひとつは渦を巻きはじめ
- 平成18年1月号を以って俳誌「青玄」が終刊となった。主宰伊丹三樹彦の健康が主な問題だったが
その元で地道に創作活動をしていた何人かの作家達がまた新たな出発をしようとしている。その先頭に立つ
のが彼女である。最近第2句集を見せてもらったら、口語で表記も現代仮名遣い使用で、ぜんぜん違和感も
破綻もなくごく自然に俳句形式を受け入れている。よほどの鍛錬があったのだろうと、俳歴を見ると昭和56年
からの入門。第一句集から12年間の俳句を纏めた句集であったので、納得した。俳句はつくづく難しいと
思う。上手いからと言って初学時代の、人真似からの発想、句作りを続けているともっと上手い人が必ず
いるものだから、二番手集団のままか、ぺらぺらの評論家にならざるを得ない。今は活躍できても、必ず
次の集団からの追い上げにあう。かといって、功を急ぎ捨てるべき句まで発表してしまっては、せっかくのいい句が
評価されなかったり、周りを怨むなんて最悪なことになる。作品が一番雄弁にその事を語る。地道に謙虚に
楽しく作りつづける以外ないようだ。
- この町に軒置いてゆく秋燕
- 「帰燕」「去ぬ燕」ともいう。燕が南方に帰って行くのである。昔から代々日本に渡ってきて
巣をつくり、子供を産みそして暖かい国へ帰ってゆく。軒置いてゆくという捉え方はこの町の人の側の
別れを惜しむこころがよく表れていてほのぼのとする。そしてまたこの軒に来てねと願ってもいるのだ。
地球温暖化で、この先どうなるのだろうか。もしかしたら子育てをするこの地の方が故郷となり、もっと
北へ渡りをするのだろうか。小動物が生きづらい世は人も生きづらい。
「初雁に富士の全貌迫りくる」「音たてて六月母は骨となる」
「ごうごうと風紋凍る日本海」「立ったまま眠る青年弱冷者」「赤とんぼここは夕日の溺れ谷」
「どうしても引けない一歩雨蛙」(第2句集「鰯雲」)
- (H19年7月18日)松永 典子
柴田雪路
- 潮境さだかなる日の秋つばめ
- 東海地方岡崎在住の作者。徳川家発祥の地であり側には世界のトヨタのある旧挙母(ころも)の
豊田市などもある。度々浜で吟行し雄大な太平洋を眺めていた。転勤族で「沖」の支部を転々として
いた私も一時期大変お世話になった。育児中の若い時期に夫君を亡くされ、俳句を心の縁とされ人望も厚く
何よりも努力家であり巧かった。毎月百人近い参加者のある東京句会へも積極的に投句、好成績の裏では
多作多捨を実行。最初の6年間の作品は全て捨て、その後12年目の第一句集。子育てに一段落してからは
日本舞踊も始めた。
- 鯊を釣る父の無口につき合へり
- とにかく手堅い。分かりやすくて何かを表現するというのが一番難しいのだ。基礎を作ってから
独自の表現をという昔からのやり方が今は疎かにされて、ちょっと面白いというだけで取上げられる。結果
、作家生命が短く使い捨ての1発屋になってしまう。せちがらくスピードだけを要求される世では仕方の無
い事ではあるのだろうけれども、だからといって長くやっているだけで、ちっとも緊張感のない巧いだけの
作品を延々と作り続けるというのもどうだろうか。ある程度の時間と緊張の深さを併せ持つ作家の出現
はもう不可能なのだろうか。作品本位というより出版不況による政治的な力のほうが優先になってはいない
だろうか。誤字、脱字、誤用が平気な人が指導的立場にいるってどうなんだろう。社会的立場だけで評価す
る風潮はないだろうか。
「こころざしいつも揺れゐて藻が咲けり」と強気のあとには弱気がくるのが普通の人間というもの
だろう。俳句って権威の中にあるのではなく、市井の健気さの中にあるのではないだろうか。
「となりより男扇の風もらふ」 「亡き夫と並ぶ齢の初鏡」 「夫のゐる黄泉に音して落椿」
「夢にくる夜釣りの夫の黒づくめ」 「しばらくは星の片よる大花火」
「手花火の闇の深さに子をのこす」 「盆過ぎのどこかに刻を余しをり」 「客として次男を泊める霾ぐも
り」「世辞言はぬ長子を恃む若布饅」 「恋ひとつはじまる予感春着の子」
「舞ひ終へて帯解く軋み雁渡し」 「身の紐を解きたる青嶺泊りかな」
「遠き子に恙は言はず梅雨の月」 「春愁のはじまりとなる売言葉」 「言ひ過ぎて団扇はげしく使ひ
けり」 「流燈を情なきごとく突き離す」
(第1句集「白扇」平成2年1月鳰書房)
- (H20年8月1日)松永 典子
田代青山
- 新涼や父の遺品に油差
- もう亡くなった父の整理もすみ、暑かった夏もようやく秋風に冷まされようとしている。改めて父の仕事場の
整理にかかったら、寸前まで使っていたらしい油差が出てきた。物や道具を大事に管理し、心のこもった父の手仕事が
今更ながら偲ばれる。油差が、未だに越えられない存在としての父を象徴していてとても印象的である。
- 首を打ち合へる背高泡立草
- 北アメリカ原産のこの帰化植物はどんな荒地にも広がってあっという間に日本全土に侵入、繁殖した。手強い生命力
で多くの日本原産種が亡んだともいわれている。そんな嫌われ者であるけれど、その仲間内での生存競争も厳然としてあり、
日向争いをするというのだ。写生とはこういう事まで見つめてこそ深化するのであり、作者の並々ならぬ観察眼に襟を正す。
28年目の俳境の高みもご同慶の至りであるが、精密な画風の現代アートの個展も開かれている由、捨てられた物や使い古され
た物を見る目には鬼気迫るものがある。
「大阪の蝉シャーシャーと嘘ぬかす」「立体縫製きちかうの白蕾」
「神留守の個人情報保護シール」
「かさぶたを取ればももいろ雪もよひ」
「初髪を草石蚕のごとく結ひあげし」
「数へ日の空咬みしたるホッチキス」
「さみだれや絵具片寄る絵具箱」「さうかもうもらつた桃は食べたのか」
(第二句集「油差」平成23年9月星だより出版)
- (H23年9月29日)松永 典子
辻 直美
- 秋燕ひとの妻なる子に会ひぬ
- 秋燕とは、秋に南へ帰るつばめ、帰燕のことである。子は、若手俳人の辻美奈子。
両人とも一緒に学んだ仲。母子に説明はいらないと思うが、直美さんのおみ足は少し御不自由であり、
娘さんは助産師の勉強のかたわら10代の頃よりの俳句作家。そんな予備知識など取るに足らない母子
の絆の普遍的な密度の濃さが、秋燕に象徴されて心を打つ。もう向こう側に行くことが、帰る事なのだ。早く帰って来なさいね。と言っていた子に、又来てねと言う立場になってしまった。
美奈子さんと写った写真があるが、彼女は私の頭の上にパーと手をあげている。明るくてお茶目なハネッかえり娘。腹の底から軽口を言い合う仲だったようだ。他人の私でさえこの娘と別れるのは淋しいと思ったものだ。相当昔の話になってしまった。秋は人が遠くなる。
- 月てらてらと流木は海の骨
- 月の光に浮かび上がった流木は青白い海の骨なのだ。こういう感覚の句もあちこちに散見
できて、上手い作家である。その上「帰省子の家揺るがせて歩くかな」の愛情深い眼差しの中のユーモアも。
凄まじい勉強家でもあったし、誰もが持つであろう心の闇を、売り物にしない潔さもあった。淡々として美しい人であった。(「春の構図)
- (H14年8月9日)松永 典子
坪内稔典
- 夕空が赤味噌に似て燕去る
- 秋の燕である。夕焼けの残照の水の色。
それはそれは美しい日本の夕暮れどき。
その雲や空の色を赤味噌の色に喩えた。それを背景にして燕が帰ってゆく、きっと名残惜しいだろうなあ。
いや自分の方が寂しいのかも知れない。赤味噌は、懐かしい色でもある。
意外な取り合わせが新鮮でもあるし、かと言って支離滅裂でもない。
この二物の間には、広大な空間が横たわっている。
- バッタとぶアジアの空のうすみどり
- また、似たような句になってしまったが、こちらはアジアの空。
アフリカのパンパスのバッタは半端じゃなく空が暗くなる程の群れだそうだが、アジアのそれはうすみどりだというのだ。
バッタに対する思い入れの違いかもしれない。
この作者は、諧謔やらペーソスといった俳にこだわった仕掛けがとてもうまく高い人気を誇っている。
しかしそれらは、ただの放縦ではない。
しっかりした古典の素養と、常に何かを考えたり知的好奇心を保っていく為の前向きな姿勢に裏付けられている。
自身で作り上げた自分の像に妙なリアリティーがあるのも実はとても知的な見えない計らいがあるのだ。
この作者を「知」の人だと思っているのは私だけかもしれない(坪内稔典句集)
- (H13年9月8日)松永典子
中島砂穂
- 後の月どの靴先も濡れている
- あとがきによると、数年間のアメリカ生活から帰国してから俳句に出会ったとある。感性も発想
ものびのびと、現代仮名遣いの口語調でとても明るい。やや散文的な句も散見するが、基本も心得ていて
口語調の俳句にありがちな破綻が少ない。新傾向は、そこが魅力でもあるけれど才に溺れるタイプが
多いので、作品としてなかなか残りにくいのが現状だろう。基礎をつくるのに15年の年月は無駄ではない
のだという事をこの句集は教えてくれているのではないだろうか。
後の月、いわゆる十三夜。陰暦
9月13日の月。名月に対していう。少し肌寒く淋しい。何かをしての帰りか何人かでやってくるのだが、
どの靴もぬれているのだ。それだけの事だが何も言わない事により十三夜の趣が漂う。後の月には抒情より
も叙景が、主観よりも写生が、取り合せとしては奥深くなる。
- 片脚がどうしても浮く茄子の馬
- 盂蘭盆会で先祖の御魂を送るための茄子の馬。四本の脚をつけるのだが、どこか重心がつりあわ
ず、どう立たせても地に付かないで浮いてしまうという句。なかなか上手い句だ。目が利いているし、
独自の発見がある。不器用な性はご先祖様からの賜り物か、ほのぼのとする。
「八月の鯨墳墓のごと浮上」
「夾竹桃ゆさゆさマッチ擦る匂い」 「終戦日カッコウと鳴く信号機」「満月の出入り口かも河馬の口」
「わたくしのレールは何処へ冬銀河」 「鉄瓶は膝抱く形寒の入り」「襖絵にわっと逃げ込む花吹雪」
「春雲のように身に巻くバスタオル」「片栗粉きしきし溶けば流氷来」「啓蟄のラップの端が見つから
ない」
(第1句集「熱気球」平成20年9月ふらんす堂)
- (H20年9月30日)松永 典子
中谷仁美
- 新米が届く母には母の闇
- 新米が届いて心は浮き立つ稔りの秋。母も水加減を考慮に入れながら炊き立てのご飯をイメ
ージする。「今日は新米よ」と特別のご飯をよそう時はうれしそうだ。子供心にも幸福な一場面で
ある。ところがこの作者には、母としてある事のその奥には、母なりの闇が横たわっている事が分って
いるのだ。29歳教員。まだ独身らしい。母は団塊の世代前後だろう。物質的には恵まれて育ってはいて
も、母の背にある翳りや光、一人の女性としての生き様などへの反感やら共感やらが複雑に入り混じって
見えてしまう。
- 待たせてるつもりで待って赤蜻蛉
- 青春も後期の、若者の気分がうまく表現されている。散文すれすれなので、韻文の緊張感にはや
や欠けるが赤蜻蛉の本意がぴたりとくる。ここが俳句の恐さでもあり強みでもある。
一般的に作品群として若者
の創作を見ると、これも仕方の無いことでもあるのだろうけれど甘い甘い句が混じって、何も俳
句でなくともと思われる作品もちらほら。余分な言葉が不用意に置いてあったりもして
、ここを直せばもっと締まるのに惜しいなと思う事もしばしばである。師に付く前の句を全部捨てた
(中堅以上の結社では当り前の事だった)私の僻みもあろうが、鑑みるとそれは正解だったような気がする。
たとえば「山笑う靴ひもきゅっと結ぶ朝」と
いう句。まず朝は要らない。意味を持たせ過ぎたり、材料の詰めこみ過ぎは焦点がボケる。
山笑うと、靴ひもをきゅっと結んだ、という配合だけでこれから意志をもっ
て出かけるという事が分るし、作者の人となりが伝わる。山笑うで、緊張している自分と世間との
ずれみたいなおかしみもある。惜しいな、この人の才能に恐れ入ってしまって提言する人がいないのだ
ろうな。たぶん。鍛錬してきた人は少数派で、絶対多数がまだ途上の人達なのだから、高点句だけを
よしとするのは本当はおかしい。自己流ではすぐに行き詰まる。まず基本、そして型破り。(形無しでなく
)さらにその句が斬新かどうかは場数を踏んだ人でなければ分らない。句会やカルチャー教室や主宰は
その為にある。若者にこそ時間があるのだから堪え性が要る。
「あほちゃう?と言いたいけれど咳を二度」
「着ぶくれてひとりでいたい夜もある」 「むくむくと積乱雲も言い訳も」
「待ち人は待ち人のまま栗ごはん」 「わたしから謝るもんか梅探る」
「夏の日の文鎮となり象眠る」 (第1句集「どすこい」平成20年創風社出版)
- (H20年8月29日)松永 典子
中原道夫
- 数珠玉に一の子分を付けてやる
- 数珠玉はずずこ、唐麦ともいう。イネ科の多年草。
その形態のユニークさから、二句一章の句が作りやすく圧倒的に多い。
道夫はこれを一句一章の取り合わせという荒業で料理した。そういえば道夫の句は一句一章が多い。
平板になりやすい形を思いもかけない発想でくらりと裏切ってくれる。
- ほほづきを舌下にしまふ愚と鳴りぬ
- これはこれで実にユニークな形に仕上げた。しまふで切れているが意味的には切れていない。
ココまで読んだ人がさあどんな取り合わせ?と待っていたら並列で、切ってあげないもんねと言っているようだ。
ほほづきが舌下でぐと鳴ったのである。ただそれだけの事。愚と鳴ったのだと視覚的に遊ばせた。
作者は生まれ付いての遊び遊ばせ上手であり、表現者である。
かつて仕事でアートディレクターとしての米国の賞を軽々と受賞したり、俳句で俳人協会新人賞に続けて協会賞も受賞。
料理はプロ級でNHKにも出演。歌も半端じゃなく上手い。
歌舞音曲、書画骨董と数え上げたら限がない。そしてあのラブリーな風貌。
天は二物どころじゃない、すべてをこの蕩児に授けている。
と見えるが、それにみあうだけのとても繊細な心遣いや努力を人知れずやっているのだ。
やれてしまうというのもまたすごいのであるが。(歴草)
- (H13年10月1日)松永典子
秦 洵子
- 鳥渡り膝といふこのぬくきもの
- 巧さでは定評のある作家だった。知命の句があって50代での第一句集。風貌も句風も透明で繊細で
美しい。登四郎もこの人を句会の最高点だけで喜んでいる作家にはしたくないと、未来を嘱望していた。
登四郎の期待を裏切らず、常に脱皮を心掛け、はじめの美しい蝋人形に少しづつ血が通っていくような感じ
だったと言う。作風への目覚めであり人間への目覚めでもあったと。よく勉強はするが孤独な人である事を、
ちゃんと見抜いていた。
- 思ひ入るすきなくさくら冬芽なり
- 自然描写の中に巧まぬかたちで自分の思いを滲ませるのに卓抜で、この人は先天的にうまさを心
得ている作家である事が分るが、一度成功した手法に甘えず、もちろん人の成功作の二番煎じをよしとしな
い潔さもある。
「遠鳰が見えて身うちに死者ひとり」
「菊人形おのれの闇をもちはじむ」 「喪の家のふしぎなひろさ寒明くる」「病む父に杖ひとつあるさくら
冷え」「寒に入る身のおもたさの常着吊り」 「ベレー帽かぶりて鳰に似たる父」「不意に子が他人めくな
り羽蟻の夜」「雲の峰より帰りたる子の皓歯」「人寄れば人のくらさやねはん寺」
(第1句集「鳥の歌」昭和58年牧羊社)
- (H20年9月18日)松永 典子
広渡敬雄
- 白桃に窪みや月に静かの海
- 白桃の窪みから月の静かの海を連想した。夏から初秋にかけて出回る桃はみづみづしく、ビロード
のような手触りは蠱惑的でもある。
修辞法のひとつで隠喩というのがある。「如し」や
「ようだ」等を使わないで内的外的属性の類似によって同一化する技法だ。俳句の場合はしっかり切って
並列的に象徴させる事が可能。短いからこそ、この手が使える。一つ間違えると散文になりかねない。
以前、名詞と名詞のサンドイッチはあまり頂けないといったら、虚子の句にこんなのがあると言ってきた
人がいたが、切れが分っていない。切れの中には形式上の軽い切れと、リズム上の切れ、意味上の切
れがあり、そのどれかが繋がっていたら切れていないから他に切れていても二重の切れにはならないのだ。
問題は何の脈絡もなく上下に置くだけで工夫がないことにある。虚子の句はつまらなくてもちゃんと俳句
になっているから単なる稚拙なものとは一線を画するし、持ってこられた数句はみんな立派な俳句だった。
この句は対象に適度な距離があり具象もしっかりしていて並列の比喩が印象鮮明。命の不思議な
繋がりをも暗示している。
- 無花果食ふ少し眼鏡のずれた人
- 無花果を無心に食べる隙だらけのこっけいな表情が伝わってくる。この人の性格まで想像させて
楽しい。白桃も無花果も、秋の季語。朝顔やカンナの花を夏の季語と勘違いしている人がいたり、
「布団」だけで季語になるのではなく「布団干す」までが生活の季語となる事を知らなかった俳人も
いる昨今、結社を軽んじてきた結果、句会の伝承的機能が薄れているのではないかと心配になる。
夕星(ゆうづつ)を金星(宵の明星)の古名と知らずにその中のひとつが・・という句を作ったり、定価付き
の句集に誤字当字があったりで(出版社の責任でもあるだろう)何をかいわんやである。勿論結社にも、
あまりにも瑣末主義で、のびのびした感性が萎んでしまい動脈硬化を起すという大いなる問題があるが。
広渡氏は基本がしっかりしている上に大変な博識、周りを明るく楽しくする人生の達人にして
山男でもある。
「雷鳥の砂浴びの窪あたたかし」「風鈴の音を削つてゐたりけり」
「枯菊を括ればじわと押し返す」 「紙漉の玻璃震はせて伯備線」「魚島や巨きな橋に跨がれて」
「みづならは綿虫の来る淋しい木」「父の日やライカに触れし冷たきもの」
(第2句集「ライカ」平成21年7月ふらんす堂)
- (H21年7月20日)松永 典子
火箱ひろ
- 爽やかや少年の抱く月球儀
- やや甘いかとも思えるが、この句はひとまづ月球儀の新しさと少年の輝かしい未来が見える。
このところ季語との距離の離れ過ぎの句が多くて、食傷気味な感がある。よほど
の事が無い限り一つの世界を創作するには、ある程度の共感性とすっと胸に落ちる納得要素が要る。自分だけで面白
がっている句や目立とうとする意図が見え見えなのは、いただけない。うますぎて、手慣れた器用な句等もそうだ。
止むにやまれぬ創作意欲よりも、物欲しげな高点句を狙っているのが丸わかりの句がある。大抵は人の言葉、人の立
場に立ち過ぎて自分の感性ではないもの等だ。選句の際は気を付けてはいるが、自分でも冷や汗が出る事がある。
せめて気を付けようという態度だけは忘れまい。
- 天高くみんなで道をまちがえる
- あやうい一句だ。述べ過ぎや散文になりかねないが、「天高く」の季語が絶妙に付いている。作者とは何度
かお話もして、大変な努力家で、それをひけらかさない教養の持ち主だと感じた。俳句の友人とはあまり私生活のあれ
これに立ち入った話より、深くて軽い(?)話がいい。あとは俳句で窺い知れる範囲が、とても
ここちのいい間柄となる。程の良い淡交はなかなかできないものだから貴重である。
[冷奴賢弟愚兄の兄のほう] [硝子戸に森がゆがんで夢二の忌]
[冬晴れを何度もバスがバックする]
[バファリンを服めば聖夜の風の音]
[年詰まるビリケンさんの足の裏]
[NTTへ行ったり来たりつばくらめ][ゆく春をぽつんと赤い乳母車] (第三句集[えんまさん]平成23年9月)
- (H23年9月編集工房ノア)松永 典子
松村武雄
- むらむらと越えたきものに土用波
- 実業界で要職にあり多忙だった氏は、ゆっくりと確実に俳人としての地位を固めていった。若い人
が多かった「沖」において力の割には同人になるのが遅かったらしい。それでも真面目にこつこつと謙虚に
創作を続けた。もともと詩人の北村太郎を双子の兄に持ち、連歌では相当にならしていた位の実力と資質の
持主である。謹厳で多くの人の信頼を受け、大企業の大仕事をしながらの作句。作品がやや堅いということ
も十分に心得ていて、「沖」の新しさを学ぼうとして試みた作品が却って失敗する場合が多く、気になって
いたと能村登四郎に言わしめた。が、同人以後の氏の活躍は大変なものだった。すぐに頭角を現し
いい具合に力も抜け、その指導力にも眼を見張るものがあった。それでも奢らず、自分より若い実力者
などに、辛口の批評を仰いだ。俳句形式に絶対的な信頼を置いていた。すべっても気にせず、熱心に投句し
、実力も本物になった。むらむらと越えたきものは俳句の深奥だったか、あるいは自分自身だったか。
- 夏あかつき職退きて水のごとし
- 静かだが深い。一生の仕事を退き、男の第二章が始まる。水はいろんな表情を持つ。光かがやく
かと思うと、雪解の激しさ、出水の恐ろしさ、春水の優しさなど。
タケチャンマンと自称し、多勢の面倒を見、
一流の仕事と俳句を残した。創作を決して侮らず、詩人の兄を敬い、軽妙な語り口でサービス精神旺盛な本物の大人
だった。
実は、この7年後に第二句集
「雪間」を上梓し、兄北村太郎を追うように急逝したのである。苦闘した作品は確実に残っている。
「雁わたる空に入江のあるごとし」「消えてより酔深くなる大文字」「心さみしく富めるあり枇杷の花
」「ちかごろの短気をかしく桜冷」「酔ざめにありありと冬の魞が見ゆ」
「熱燗に涙し笑ひみな老ゆる」「良夜にて蜘蛛膜下なる翳おもふ」「蚊がひとつ室内楽より出できたる」
(第一句集「冬の魞」書肆山田)「兄死後の北窓塞ぐこともせず」「元気かと雪の絶間の墓たたく」
(第二句集「雪間」書肆山田)
- (H16年7月30日)松永 典子
水上博子
- 赤チンの膝も並んで木の実独楽
- 今は、よい傷薬や傷テープなどがあり、すぐに手当ができるようになっている。というより、なかなか
怪我もしなくなった。ちょっと昔までは、みんな外で暗くなるまで遊んだものだ。小さな怪我は当たり前だったし、
今は無くなった赤チンをなんにでも塗ってまた外で暗くなるまで遊んだ。そして今。兄弟の数も子供も少なくなり、
高価なゲームや(それはそれで面白く、器用さの目安や苦労の末の達成感や人生の苦さも教えてくれるが)お稽古事
や塾等子供もいろいろと忙しい。昔は事故で無くなる子も多かったが、はたしてどちらが心身共に豊かだったかと
いうと、なんとも言えなくなる。それだけでは困るがノスタルジーの句もたまにはいいものだ。
- 稜線の縹に暮れて温め酒
- 縹(はなだ)色は薄い藍色で、襲(かさね)の色目の名でもある。「縹色の唐の紙に包みて」(源氏物語絵合)
彼女は古典への深い素養があり、小さな句会だと誰もわからないような古語を使ってだいぶ損をしていたような所
もある。その点で、評価は難しいが、句会に出すという事はたとえ難しい言葉であっても、前後の言葉の配置によ
り判らせるという作者の配慮も必要である事を身につけられたようだ。それが俳句による技術である。技巧を凝ら
し過ぎても見透かされるし、重すぎても、当たり前過ぎや凡庸過ぎるのも詩としての緊張感に欠ける。日本語は豊
かだからこそ、慎重にならざるを得ない。中身がある人ほどその辺をよく知っている。
「ポケットの家出の苞のさくら貝」 「からくりのとんぼがえりや信長忌」 「無花果はジャムに恐竜はいし
ころに」
「貼るカイロリュックに皇子の眠る山」
「垣間見に始まる恋やなめくじり」「このあたり八の宮跡夏よもぎ」「子規居士の柿は蔕までかじられて」
(第一句集「ひとつ先まで」平成22年9月ふらんす堂)
- (H22年10月7日)松永 典子
森山夕樹
- 雁来紅に月光のいろ残りけり
- かまつかとも葉鶏頭ともいう。雁の来る頃もっとも鮮やかになり目が覚めるようである。
「昼間の
鮮やかな色のかまつかを実(じつ)とすれば、この明け方のかまつかはまさしく虚のように淡い。描線を消し
去ったうつつの姿とも見えて一層美しいのだ。それも具象的把握を捨てなかった成果と見たい。」と、山上
樹実雄氏は夕樹の第二句集「花屋敷」に鑑賞文を寄せている。もう一人、同じく関西在住の岡井省二氏もまた
同句を取り上げての一文を、沖誌に寄せている。「かまつかによべの月光を思っているのであろう。もしくは
さまざまな月光のいろを見てとっているのであろう。それがかさなっているのであろう。これまた端的に言い
切って言いおえてはいない。直截なこの『けり』はまことに由々しい。このむしろ断定の快感こそが夢幻の
原動力だ。やわらかくて鮮やかで、淡くて深くて・・・このかまつかの紅はたしかに見えてくる。その紅
の艶は余韻をいつまでも残して止まない。」と。
- 出で入りのしづかに芙蓉ひらきけり
- 岡井、山上両氏に加え福永耕二も鑑賞していて豪華な顔ぶれが、共通してその夢幻象徴、男の抒情
と、孤愁、やさしさ等を言う。第一句集「しぐれ鹿(鳰書房)」での(鮮度の高い、すぐれた句集であったが、)
やや甘い表現、やや生硬な抒情が、7年後のこの句集ではもっと洗練された形で作者独自の観念の世界を築き
あげている。難しくてだれも手をつけたがらない分野でもある。「馬酔木」「南風」「沖」でじっくり独自の境地を
開き、後に鈴木鷹夫「門」の許で、関西の雄として活躍、これからという時に夭逝した。船団の内田美紗氏は、
血縁にあたる。女性主導のファンが「月さして知恵をさづかる葡萄の木」を碑に残したという。
「紅梅や武士ならば斬る人ひとり」「窓の灯のしづくとなりし落葉かな」「啄木鳥やほとけの山に径
うすれ」「梟に夜はくるほしきかまどの火」「てのひらの蝉鳴く感情線にふれ」
「新緑や飯盒に火の這ひまはり」「注射器に血のくらくらと桜満つ」「お札所へ蓼や木槿や晴れつくし」
「峯ひとつしぐれて春の夕日さす」「ほつ枝またしづ枝の梅のしづり雪」(第二句集「花屋敷」永田書房)
- (H16年9月15日)松永 典子
安居正浩
- 酢豚定食おとなしく待つ無月かな
- 若い父親と学齢前の一ときもじっとしていない男の子。残業ばかりであまり子供の相手もしていなかった。
今日は久々のノー残業デー。いつも多忙な妻に代わって、きょうは自分が子供を連れ出してやろう。中秋の名月も
見てみたいし。だが生憎の曇り空。月は見えなかったけれど、好きな酢豚定食を頼んで父といることの嬉しさで、
足をぶらぶらさせておとなしく待っているわが子がここにいる。これ以上の何を望むというのだ。
- 芸術と芸のはざまに吊し柿
- 芸術と芸のはざまとは、俳句の事を言っているのであろうか。それともそういうものを超えた現実のなかの
吊し柿そのものが俳なんだと?
軽い切れの「に」は、そこにあるという意味と作者がいるという意味にも
受け取れる。
妻とその母は俳人同士。初めは二人の楽しげな会話の俳句とはどんなものかと興味を持ったのが
きっかけだという。一流エリート銀行員でも、「大胆な妻の水着に近づかず」「母の日の父の居場所を灯しけり」
のようなペーソス溢れる気弱な善人の顔を持っている。師能村登四郎は、そのエリートの顔を俳人にはむかないのではと
心配したが、思い上がりや知識をひけらかすえらぶったところが無い、むしろ己がわかっている真の”知”の人
だと、10年目にして上梓されたこの処女句集の非凡さを祝福している。(春の椅子)
- (H14年10月8日)松永 典子
山本純子
- 廃船を描く人いて鰯雲
- 廃船がそのままに朽ちてゆく過程に興味を持って描いている人がいる。雄大な海と鰯雲を背景に。
作者はそれを見ているのだ。作者のこころの絵には、更にその描く人を入れた情景が浮かぶ。中身が濃い。
人は感動をしている人を見ても感動する。これ程解りやすい句だとすぐに伝わるものである。句は分りやす
い事が大事だ。
- 鳥けもの甍になって奈良の秋
- 名の有る寺院の甍。いにしえ人の物造りへの心の入れようが直に伝わってくる。花鳥風月と共に
生き、身近に感じながらの豊かな生活、ゆったりと過ぎる時間と空間。どれも現代人が忘れ去ろうとしている
ものかもしれない。便利さは本当に幸福なのだろうかとの問い。奈良の秋がよく付いている。
H氏賞受賞詩人だという。最近詩人だという人達が横紙破りのように俳句になだれ込んできているが、
せめて彼女のように10年くらいは俳句の為の鍛錬の時間を持って欲しい。自称詩人は形式を破る事ばかり
考え、性急に功名心に逸る人が多い。俳句はポエムだけではないのだ。諧謔だけでもない。加えて伝統
と言う言葉に異様に嫌悪感を持っている人もいる。大学教授であろうと高名な詩人であろうと1会員から
始める、無記名での選句を、という原則は残るべくして残ってきた伝統的方法論でもあるだろう。
「塩借りに丸太を渡るキャンプ村」「なにもかもまたいで歩く海の家」
「白鳥の首のアーチのように待つ」 「笹飾る留学生のひらがなも」「冬の夜も寅はバターになりやすく」
「忍法はここに伝わる軒つらら」「なくしもの三回探して竜の玉」
(第1句集「カヌー干す」平成21年9月ふらんす堂)
- (H21年10月2日)松永 典子
渡辺鮎太
- 見せてもらふ月下美人と人の妻
- 意味はよくわかるし、情景もすっと伝わる。月下美人は晩夏の花の女王。夜半に咲き、数時間の命である。丹精込めて咲かせた人はその喜びを近隣の人にもわけてくれる。
会社人である作者はさして変化のない日常の中で、ある日、妻帯者の同僚が今夜月下美人が咲きそうなんだ、夕食でもどうだと招待された。ちょっと心がはずんだのは、見た事の無いその花の事の他に、若い同僚の奥さんも見てみたいと。口には出さないけれど。
- 逢うてゐて月の遠さを思ひけり
- 何の逢瀬か。もうどきどきする年代でもないが、自分では妄想を膨らませてちょっとロマンチックな気分をと。たとえ何でもない仕事上の面接であっても、眩しい異性だったりするのだ。
ところが、やっぱり仕事は仕事。現実はさっぱりしたものだ。自分だけの世界では、あの月の遠さだけが際立って感じられた。
ちょっとした日常のなかに、ふと通り過ぎる別の人生。
(鮎)
- (H14年9月6日)松永 典子
戻る