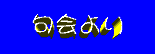止り木を跳下りしより春の猫
- 居酒屋やスナックの止り木の事だろう。常連客にも可愛がられて、アイドル的な存在の、店で飼っ ている猫、常に端っこの止り木に大きな顔で陣取り、ごろごろと喉を鳴らしたり、熟睡したり・・。この猫 を目当ての常連さんもいて、酒の具等のご相伴にあずかったりもする。冬の間は怠惰なその有りようが人を 和ませる。そんなタマちゃんが、すっと椅子を飛び下りてしなやかに伸びをした。それがこれから始まる恋 の季節の予兆なのだと。春の猫というゆったりした語感がかえってすさまじい恋の嵐の時代の始まりのイメ ージに似つかわしい。
万愚節半日あまし三鬼逝く
- 岡山県出身の西東三鬼の忌日が4月1日。新興俳句の旗手で総合誌「天香」の編集長を務めた。
「水枕ガバリと寒い海がある」で有名。その死を、もう宿痾の病を得ていた波郷が悼んだ句。馬酔木に
拠っていた松山市出身の波郷は「鶴」を主宰し、草田男・楸邨と並び人間探求派と称された。この句は
「借命(しゃくみょう)」より後に出た「酒中花」にあり、力は衰えるどころか益々冴え渡っている。7年後
の昭和44年11月21日波郷忌となった。
没年まで「鶴」主宰。
「行春や吾がくれないの結核菌」 「祝婚やミモサのもとに咳こぼし」「とまり木に隠れごころや西行忌」「ひとつ咲く酒中花はわが恋椿」 「境涯の辛夷咲く句を遺しけり」「妻在らず盗むに似たる椿餅」「釣堀に水輪あふれぬ花の雨」 「三鬼忌の雹の水輪の大粒に」「短夜や誰が出でゆきし門の音」
(句集「酒中花」昭和43年東京美術) - (H19年2月3日)松永 典子
干魚の口の藁ぬく余寒かな
- 長谷川双魚門で活躍をしていたが、師の急逝に会い、登四郎門にも入って勉強を続けた。屈折 した自己顕示欲が無いので、重くも堅くもならず爽やかであると、序文で長谷川久々子が誉めている。 つまりしつこく自己顕示をしなくても、本物であったら作品の方が立ち上がると。彼女の句は、俳句の伝統 を踏まえながら、写生の域を越えているとも。育ちの良さと、表向きだけではない無駄とも思えるような 本物の勉強が、ゆったりして動じない余裕を産むのだ。
火消し壷しゆんと鳴りたる夕桜
- 登四郎が採ったこの句、夕桜がぴたりとついて動かない。俳句はうまくなければねと、よく句会
でも口癖のように言っていた。上手過ぎる句もあるけれど、それは厳密には上手いとは言えないとも。
高点句ばかり狙っている間はまだ初心、うまいのは当り前で、人を感動させるというのは技術の上にある
のだとも。20年ほど前彼女とよく大和路を歩きまわった事がある。父親ゆづりの草花の薀蓄から歌舞伎から
美術や東西の古典まで、その教養の深さに感嘆したものだった。
「桐の花ぬれゐて源氏一の巻」 「浜おもと萎れて祖母の端切入れ」 「合紋の会釈をかはし島桔梗 」 「蔀戸に冬日のとどく願ほどき」 「初花や鞄小さくをんな旅」 「半衿をつまみ洗ひに花すもも」 「仏具屋の瓔珞ゆるる朧かな」 「梟や月光の木々濡れてをり」「先噛んで下ろす唐筆冬かすみ」 「白粥を吹きくぼませて木の芽晴」「青葉しげりて三音のけぢめかな」「梅ひらく明るさに水走るかな」 「うしろから釣瓶落しの猫の鈴」 「山の影より新涼の伝馬船」「武者隠しより光る湖笑ふ山」 「満目のすすきの枯れを伊賀郡」青樹同人 (第1句集「草づくし」平成1年3月本阿弥書店) - (H20年3月4日)松永 典子
- 野火守の退路にも火のまはりつつ
- 40ヘクタールもの淀川の葦焼きはすごい。宅地化の進んだ昨近は、次第に野焼きも規制の対象になりつつあるとか。有名な行事にしか登場しなくなるのかも知れない。
実は、彼女が角川俳句賞を受賞した頃たった一度句会をともにしたことがある。私が大阪に来てすぐの頃の「淀の葦焼き吟行」での事。淀川の寒さを知らなくて、スカートで参加していた私に、その頃出初めのレッグウォーマーを貸してくれたのが彼女だった。
すでに鶴の同人でもあったが、とても気さくで優しい感じの美人が、ひと度火が放たれるととてもきびきびと動き、その目は厳しい仕事人のそれであった。野火守の厳しさと一歩もひけをとっていなかった。
- 病み臥すや蟇の恋してゐるときを
- この頃に大変な病気をされたらしい。(春の日や松一本を恃み臥す)(巣ごもりの雀に近き病臥かな)(点滴に右手とられぬつちぐもり)等仕事盛りの痛ましい句が並ぶ。
学生時代からの30年間、厳しい「鶴」俳句の洗礼を受け第一句集「群萌」は成った。 若いからといって甘やかさないよき道場を得たことは、その後の彼女の作品群により研きをかけた。時々は、離れてみたり、否定してみたりはしても、完全には手放せなかった俳句。そういう経過なども経て、修養を積んだ作品の良さが光る。
病気の時考える事など個人によって違うと思うが、多かれ少なかれ死と向き合う形になるのか。生活を共にしてきたこの俳句形式が、振り払っても振り払っても呼びかけてくる。人生の彩りとしての楽しみの道具だったはずが、この見えない心の五七五は、自分の命を吊っている細い細い(でも思ったより強い)蜘蛛の糸となっている事に、ある日気づかされて愕然となる。何かの目的でもなく手段でもなく、生きることそのものであったと。(第二句集「聞香」)
- (H14年3月20日)松永 典子
胴ながきわれあり桜ふりつづく
- 20代の作。自我と向き合い他者との距離をはかり、混沌の熱気の中で敗北しか見えない時代であ る。胴ながきわれが何物か、桜がふりつづくばかりである。醜い己にことさらにこだわる。それだけ純粋 な時代でもあるのだ。20代でなければできない句かもしれない。
かげろふやバターの匂ひして唇
- 唇の匂いが先ほど食べたトーストのバターの匂いなのだという。若い頃は、もう色んな物が欲し
くて欲しくて、なんでもガツガツと自分に足りないものを補おうとする。心の飢えや渇きに殊に敏感であ
ったり、分かりやすい物欲であったり。あるいは性欲という事も考えられる。ピーナツバターの残ったまま
のキスで、ピーナツアレルギーの恋人が亡くなったというアメリカのニュースがつい最近報道されていた。
あるいは共に朝を迎えた仲の軽い挨拶だったかも。
ねっとりしたエロティシズムは、俳句では駄作 や言い過ぎの句が多くて辟易するが、直接的な表現をしたい人は短歌を作って欲しい。七七でたいていの 事は言えてしまうから、言ってしまっても後の昇華ができやすい。俳句は直接的な表現には向いていない。 余程力量が必要なのであるが、初心者ほどどぎつい表現で人の気を引こうとして大失敗をしてしまう。 技術が無いからだ。この人はその点、抑制が効いていて、それでいて大胆に青臭い混沌を細心に表現して いて見事だ。
「鷹」同人を経て現在「澤」主宰。
「尾を水平に猫の恋了りけり」「死体役の俳優に蝉鳴きにけり」「浅蜊の舌別の浅蜊の舌にさはり 」「学僧の百姓面や帰り花」「べったりと羽子板卓に置かれある」「ふはふはのふくろふの子のふかれ をり」「芋虫のまはり明るく進みをり」「谷崎忌カットグラスの稜を撫で」「蛇穴を出て夕暮の欅の木」 (第一句集「砧」昭和61年牧羊社) - (H18年1月8日)松永 典子
雪解川わきめもふらず流れけり
- 早春の川、それもかなり大きな、雪解の水が各支流から集まってくる所の急流であろうか。わきめもふらず一心に流れてきているのである。まるで目的があるように。
作者は「狩」の若手で、俳歴25年のベテランでもある。この人の評論には定評があり、鋭敏な言葉感覚としっかりした文体構築で、いつも安心してその論に耳を傾ける事ができる。雪解川ではこの場合切れていない。これは一章でできていて、最後のけりで切れている。だから説明ではないのだ。けりを付けるという事はこのことを言う。季語の説明をしたら、切れ字を入れるか、体言止で最後に切る事をしないと、ぶつぶつ切れたり締りがなくなったりする。「ほうたるの火の精にして水の精」と鷹羽狩行の祝句。 ことありて帰るふるさと花辛夷
- これは二句一章。ふるさとで切れて、花辛夷が実に合理的、象徴的に使われている。やや付きすぎの感もあるが、しっとりとしたこのような句は、できそうでなかなか出来ないものなのだ。初心者はどんどん冒険するがいい。そして傷つこう。多作が悪いのではない。多発表が悪いのだ。捨てる事をしなければ、自縛の果てに、評価しない他人を恨んでしまう。先人達は心理学の分野にも対応しようと句会なるものを洗練された形で残したのだ。記名のあとでの評はどんなベテランでもエコヒイキが入ってしまう。句会で無記名のうちに、高点句だけがよいのではないと発言できるベテランが真の主宰者なのだ。(第二句集「水精」本阿弥書店)
- (H15年2月23日)松永 典子
- 三月の水をあつめに水走る
- 三月の水とは、ほかに雪代とか雪解け水とかの言葉も喚起する、早春の水の事であろう。
駘蕩とした春の川よりは、すこし早いまだ冷たさの残る川。雪解けによる春出水という言葉もある。 水が水をあつめに走っていると表現した。なんと清浄な激しさであろうか。積雪地帯では川や海が濁るほどだという。そういえば雪崩の季節でもある。地上では、春一番。春の嵐。ライオンのように始まって、一気に春。季節の変わり方が劇的だ。
- わが行方春泥に靴とられゐて
- 女教師で一女の母。夫は夏石番矢氏。
春泥に靴をとられるという具体的な所作と響きあって、行方という言葉が暗示するものに何か象徴的なものを感じる。精神的に苦しい何かで、進退窮まった状態であろうか。作風の転換期でもあったのか。
初学時代のきらきらした彼女の一部始終を見てきた者にとって、それは一遍の美しい私小説を読んでいるようだった。身辺詠しかり、感覚詠、学生時代からの磨かれた表現技術、素質ともに申し分なく、時に激しく、時に切なく、常にある種不思議な光を纏っていた。
父親を早く亡くした内面の起伏が影となり、彫りの深い作品に結実し、読む人の心を揺さぶった。正木ゆう子氏はその頃の山口百恵に雰囲気が似ていると表現した。
わが道の青きを踏むもあとわづか
白肌着おぼろの底に畳みをリ
二の腕に鱗のかけら桜鯛
と、その頃の彼女にしてはめづらしい作品群が続くが、一面では夫君と巡り合い言うなれば人生の ベルエポックとしての羨ましい記念碑的な時期ではなかったろうか。(第二句集「水の十字架」) - (H14年2月20日)松永 典子
卵白も弥生の空も泡立ちぬ
- 弥生は陰暦3月の異称。空の泡立った感覚も、花曇やら白っぽい薔薇科の木花の盛りやら霾やらの、 なんとなくふわふわした晩春の気分をよく表していて卵白のあのもったり感にも通じるものがある。この ように比喩の対象を並列に置いての配合は、ともすると強引になりがちであるが、この句は程よく響き あって心地よい。うまさは見えない方がほんとうの技術なのだ。
蝶の恋空の窪んでゐるところ
- 梅本豹太「序」、大島雄作「跋」と、感覚の若若しい作者にふさわしい句集となった。実は彼女はとて
もスロースターターで、感覚はよかったのに今一つのところで踏みとどまっていた。初学を、しっかりした
基礎力も要求される「沖」で始めた事がネックだったが、今ではそれが良かったと謙虚にも彼女は振り返
る。十数年もの初学時代の句をすっぱりと捨てて勝負しているのだ。久し振りに彼女の纏まった句群を見
て感覚だけではない本物に出会ったようなすっきりした気分になった。力みが入る事で読む者を緊張させ
たり、軽いだけの散文調で言い過ぎにもならず、器用な上手過ぎの退屈もなく、適度な軽さに、持ち前の
感覚もしっかりと活きていてバランスがいい。これからが厳しいスタートラインだという。俳句を侮って
いた昔を恥ずかしいという彼女のために大いに喜びたい。
「ラガーシャツ干す肩の辺にまだ闘志」 「解体のビルの内臓つちふれり」 「茄子の紺糠に移りし大暑かな」
「汐風に頬のつつぱる厄日前」 「寄鍋のどつちつかずの席にをり」 「毛皮店森のしづけさとも違ふ」
「雪卸すいい青年になつてゐ し」「ふかふかのセーターを着て脛齧り」「竹の根のいよいよ真青寒造」「卒業歌こずゑまで水昇りつめ」 「水嵩の常に戻りぬ石たたき」 (第1句集「空の素顔」平成21年1月本阿弥書店) - (H21年2月9日)松永 典子
葉に涙ほどの塩味さくら餅
- さくら餅には独特の香りと可憐な色彩による華やかさがある。その華やかさの裏には涙の味の
葉っぱが付いているというのだ。しかもその塩味はなくてはならない脇役であると、この実力派俳人が
言っているのだ。
長い間「沖」の編集長として、登四郎を助け心からの尊敬をもって師事した。 福永耕二に師事して10年目に耕二が夭逝した。その後「沖」に。第一句集「八荒」は、 15年目の上梓で、前の10年の作品をばっさり落としている。 第一句集「咀嚼音」で「馬酔木」で学んだ10年の句をばっさり落した 登四郎にとってもこの不器用さ(実力はあるのに世に問うのが遅かった)は自分自身にも通じる気質として、 親近感を持っていたようだ。50代実力派3女流として坂巻純子、北村仁子と並び称されすさまじい競争を していた。坂巻、北村両氏が50代で夭逝したのをみても、その過酷さがわかるというものだ。 しかし、この作者の明るさ、気さくさ、誠実さには頭がさがる。求道の過程は人をやさしくする。
創作欲は時に恋愛に似て身を滅ぼしかねない。自己表現に存在をかける営為は五欲よりも強いと 私は見ている。だから、名をなした人々を無条件に尊敬する。浅いところで簡単にいい句ができるわけが ない。 生きるとはどこかで見えぬ踏絵ふむ
- 江戸時代の春の風物詩であった、絵踏みの図は浮世絵で有名だが、もう使われない季語だと切って
捨てるでなく、このように現代に生かすという方法もあるのだ。器用なだけではできない句と思う。
権威やら独裁者やら国家やアメリカやテロや、その他愛するものや平和にさえ私たちはいろんな
踏絵を踏んでいるのだ。生きるとはそういう面倒な手続きがいるのだ。創作にさえ。
「豆を撒く真うしろ鬼の隠れ場所」「比良八荒血の濃くて喪の白づくめ」「練炭灰ほぐし忌明けの裏 畑」「水仙の葉折れはじめの日ざしかな」「外套のまま座す人気なき生家」「冬ざるる元栓すべて止めし 家」「小春慣れせし身にはたと老小町」「春の闇おそれぬ齢怖れけり」「豆に頬打たるる覚えなくもなし」 「看取り明かしてくれなゐの雪を見し」「紫陽花のこころ変わりに付き合へり」 「曼珠沙華溺愛の根の暗しとも」「蛍籠ゆすりて今はの火を強ひぬ」(第一句集「八荒」本阿弥書店平成1年) - (H17年1月9日)松永 典子
いくらかは残る昏さへ木々芽吹く
- 能村登四郎が絶賛した句である。退屈になりがちな自然詠での、作者自身の心の奥深さをしっかり 表現できていると言う事だろうか。人柄は物静かで、女流俳人に有りがちな、人を押しのけてでも目立とう とするタイプではない。勉強熱心でしかも本物の教養を身につけたよき時代の才媛とでも言おうか、 一句一句大事に作り、しかも潔く捨てる。常に高点句だけを目指して短期間に伸びた人の句集には、もう すでに誰かの似たような句となって真似したり真似されたりの陳腐さが並ぶ事になって面白くない事が 多いが、彼女のように目立たないけれど基本がしっかりして時間をかけて鍛錬した人の句集は読めばすらり と心に届く。
吊りしまま出遅れてゐる春の服
- 心弾む春の服を新調して吊ってあるのだが、ぐずぐずしていて出遅れているのだ。気後れやら、計
画倒れやらでなかなか服を着る機会が訪れない、女性なら誰にでもある心の綾を具象で言いとめていて共感
できる。「都合よきときには老いてゐのこづち」「紙懐炉見当外れより出でぬ」等の句と共に、これらには
佐山さんに全くなかったユーモラスな味が出て来たのに驚いている。年齢が深くなるにつれてそのような
俳諧性に富んだ句を見せることも作家の幅だと思って大いに期待したい。と序文は結ばれている。
「母の日のそれらしき人乗り降りす」 「数へ日を割りふつて母訪ねる日」 「母のなき母の日が来て胡麻よごし」「裏海の続きのうねり芒原」
「風のなき刻コスモスの疲れけり」 「別れ来てまた連れとなる鰯雲」「着膨れのやっぱり伝言つたはらず 」「点となるまで炎天の子を送る」
「子離れに格好な北塞ぎけり」 (第1句集「花前線」平成7年12月本阿弥書店) - (H21年1月4日)松永 典子
春暑し立看板のかはかぬ字
- 暑くなるという事は湿度も上がり、なんとなく身体もじっとりしてくる。ベンチのペンキ塗りたてのよう にまだつやつやとした濡れいろの立看板が目についた。晩春でもなく、暮春でもなく、春暑しという語感が ぴったりだったのだろう。立看板の濡れ色という具象がこの周到な季語を選ばせたとしたら、作者は若くして 既に句の骨格がしっかりしていたという事になる。森岡正作との二人句集「卒業」(私家版)において、 後の師となる石川桂郎、能村登四郎にそれぞれ序文を頂いている。幸福なニ俳人の出発の句集である。
梅雨深む赤せうびんの一つ音に
- 赤しょうびんは翡翠の一種。梅雨時によく鳴くので雨乞鳥などという。キョロロロとよく通る涼し
げな声が梅雨どきの雨を呼ぶ。
馬酔木系の結社はほとんど若いからとか専門だからといって特別扱い をしない。主宰、副主宰以外は、会員から始めてちゃんとした実績を積まなければ当たり前の事だが、同人 になれない。遅速の差はあってもある時期猛勉強が必要になる。人はみな自己評価は実物より高めである。 国語教師であろうが、大学教員であろうが同じ土俵だと國學院閥もあった沖で能村登四郎も常々言っていた。 それが実力のある若者を育てるのに役立ち、信頼感と安定感をもたらす。
「風土」同人、「一葦」主宰。
「日に二分遅るる時計緑立つ」「つまらなくゐる雑踏の花火売」「日脚のぶ牛乳壜のくもりいろ 」「鳥も巣を急げり吾に旅鞄」「鶏頭の空うちかぶる微熱かな」「身に入むや黒板の字をすべて消し」 「火事に遠き家々は押し黙りけり」「かがやかに擬死ほどきけり天道虫」 「たましひのやや濁る日ぞ曼珠沙華」(第一句集「卒業」昭和47年共著私家版) - (H18年4月2日)松永 典子
鳥雲にこんなに沢山父の骨
- 鳥雲に入るという季語。秋冬に渡ってきた候鳥類が、北方に帰る事。鳥帰る。
父の死を受け入れる のには時間がかかるものである。切実な母の死とは違い、どこかぼんやりとして徐々に大きな悲しみが やってくる。「うぐいす餅が出たというのに父死にし」「父は怨みのこさず逝けり夕辛夷」「父に搏たれし ことの一度を夕桜」等から作者と父の関係とその人となりがなんとなくわかる。骨、うぐいす餅、夕桜など の具象がいっそうその悲しみを増幅している。 信じあふ湯呑がふたつ桜の夜
- 信じあう間柄とは、「門」主宰の、優れた俳人であり助言者であり夫である鈴木鷹夫氏の事。いろ
んな事をくぐり抜けて来たという同志としての存在に対する安らぎが信じあう湯呑に象徴されて、桜の夜の
しづけさが、しみじみと伝わってくる。
第一句集「夏のゆくへ」は村山古郷門から始まり「季節」「鶴」「沖」を経て30年に及ぶ句歴の中で、 初期の作品は総て除き、「沖」誌発表句(中央句会での手応え句、主宰選句)の中から更に主宰に選んで頂い たが、まだまだ深みの足りなさを痛感していると書く。(「薪束の胴締め寒のにはかなり」)。それから 5年後の第二句集「秋の卓」では、父の死、鷹夫主宰の「門」創設など激動の日々の中での作が並ぶ。 虚実の間に心象をたゆたわせる沖風にあって、俳句とは頭でこしらえるものと最初から思い込んだ人との 間に大きな差があるのは、即物詠の手法を十分身につけてから机上派に順応していったためだと、林翔は 言う。気取りのない円満な人柄で、お母さん的存在はだれでもがほっとする。深刻な作品もどこか明るい。
「眼鏡はづしても炎天に変りなし」「運動会顔削るほど走りけり」「悔しさは笑ふことにし秋の風」 「饒舌をつくして冬の木となれり」「ははを思へば日の暮れの花柊」 「一位の実いく粒食べて鳥になる」「熟れすぎることを愚かに次郎柿」 (第二句集「秋の卓」東京美術) - (H16年3月7日)松永 典子
人死して時計鳴りけり春の昼
- 人はみんな死ぬ。自分の終りが即ちこの世の終末なのだ。だから終末というのはノストラダムスや 中国の君子や占師が予言するものでもなんでもない。一人一人に終末が存在する。大事な事として、生き 死にの問題以上に深刻なものはない。それをさらりと春昼のやや間延びした時計の音と取り合わせている。 人の死にかかわらず時は流れ、四季は移りあたたかい春は存在する。
涅槃寺靴一足の余りたる
- 釈尊入滅の陰暦2月(今の3月)15日に修する法要、涅槃会のお寺で、善男善女の沢山の靴が並ぶ。
そして法会が終ると波が引くように帰ってゆく人々。静かになった上がり框に靴が一足余っている。
誰のだろう。そしてどうやって帰ったのか。まさか・・。と、いろんな想像をしてしまう。この人
の句は重くれの句が多い。まだ最初の十年でこれだけの内容を句に込められるのはかなりの力量とみる。
軽々とした句が中に混じるともっといい句集になるかもしれないと思う。軽過ぎる句集が多い中かえって
目立つのかもしれない。「銀化」同人。
「幼年の写真をもたず冬鴎」 「秋旱死して平たき麒麟かな」 「囀や六十歳の象の耳」
「金輪際動かぬゴリラ十二月」 「のんしやらんのーしやらんと毛虫かな」 「着陸の爆音かぶる浮巣かな」
「爛漫の春や老人鈴生りに」「こんなふうに咲きたいのだらうか菊よ」 「あやかしの膕のびる桜どき」 (第1句集「風の忘るる」平成20年7月ふらんす堂) - (H21年3月12日)松永 典子
夜勤後の身を浮かせたる花菜照
- 看護師であり助産師である美奈子さん。大変な激務のなかから一齣の生活詩を掬いとって眩い ばかりの存在感を示す。登四郎も序文で、みずみずしい感性と理性と大胆さを感じたと記す。 昭和55年から平成6年までの15年間の句業の集大成で、青春時代から結婚後までの第一句集である。我の 強い、主張ばかりの女流が多い中、むしろ静かなゆったりとした雰囲気を持つ。充実した仕事を持つ女性 のゆとりからか、物事に動じない本当の芯の強さを持つ。俳人でもある母、辻直美さんと共に学生時代か らの俳歴は長い。初学時代は馬酔木から沖へと活躍の場を広げる。
母よりも少し未来の桜見る
- 脚が少しだけ不自由であったお母様と一緒に桜を見ているのだ。母よりも少し先の桜を。そして
未来を。美奈子さんの職業の選択の意義と意向が何となくわかるような気がするのだが、勉強会で若者ば
かりで集まったときに撮った写真の中に、冗談ばかり言っていた私の後ろで片手でパーの掌、片手で
この人ですと指さしているのがあって、とても明るくお茶目な面もあった。独身の頃の話である。若い内
は買ってでも苦労をしろという言葉の意味を私は60になって初めて本当に理解したが、美奈子さんはそれ
をよく知っていたのだろう。苦労を人に見せないでこつこつ仕事も俳句も頑張った彼女の「魚に
なる夢」はその年の俳人協会新人賞を受賞した。
「炎天へ生まるるときはたれも泣く」 「羊水は夏の夜に似し匂せり」 「体内の水あたたかに枯野 ゆく」 「魚になる夢に目覚めてなほ寒し」 「父にある聖域蒼し夕端居」 「われの名に奈落の奈の字 曼珠沙華」 「婚約のあと鰯雲つひに見ず」 「ストーブの位置すぐ決まる新居なり」 「ほの昏き薔薇の花芯で眠りたし」 「ひと捻りして年の夜の髪を上ぐ」「葱下げて音なき部屋に帰るな り」「さくら満つ生まれるまでの十時間」 「噴水のつぎの高さを待ちにけり」 「産む産まぬたはやすく いふ無月なり」「新生児あまた並びて神還る」 「会へる予感に風花のひとしきり」 (第1句集「魚になる夢」ふらんす堂) - (H20年1月10日)松永 典子
- てのひらの匂い雲雀の巣の匂い
- 少年がひとり。河馬の形態とその在りようが好きで、できたら少しでも近づきたいと願っている。
大人になって中年になって、髪に霜置く頃となっても、一日雲雀の巣を探しに行ったきりなかなか戻ってこない、そんな稔典氏である。
そのてのひらは、うっとりと見つめていた雲雀の巣の匂いがするのだ。 - 帆になって男が消える春の雪
- 少年は佐田岬の海辺で育った。人生の節目節目で、原風景の海を思い出す。隙間なく降る
春の雪。そこはまさに海。男は帆になって消えて行くのだ。春の雪で、ちょっとほっとする。
取合せを推奨するのは、俳句は一応だれにでも出来るという前提にたっての事。どうやったら平凡 でなく月並みのような亜流をうみださないですむかとの、初学者の為のノウハウを早くから提唱してきて成果をあげているが、とりわけ若い人には説得力のある方法論である。芭蕉の頃から、配合であるとか、新は深なりとか、鋼をひきのべたようにすらりとした形にとか、三尺の童にさせよとか、いろいろな方法が唱えられてきた。取り合わせはその中の一部である。俳句は詩であるとすれば、詩とは何かという考察から入らなければならない。詩は、比喩と諧謔である。ところが、俳句はそれをも内包し尚且つ形式的な制限がある。いわゆる十七音(短歌からもらった)と季語を入れるという約束事である。それさえ守れば、我々市井の者にも詩(創作)を身近なものとして楽しめる、という考え方は素晴らしかった。
何の娯楽もない時代に、随分としゃれた遊びを考えたものだ。ところが、どうしても一方向や、俗に偏ってしまうという事。それを恐れた人達が度々改革を試みて、その都度いい作品が生まれている。やがては、自家撞着による次の月並みをも孕みながら。 (第九句集「月光の音」)
- (H14年1月29日)松永 典子
中岡毅雄
捩れゐるブリキの屑や猫の恋
- 猫の恋のすさまじさには辟易するが、音感からくるそれを、視覚に置き換えた。捩れたブリキの切り屑の よう(に不快)だと。修辞法の一つに、如しとかようだと言わない喩え方の、隠喩があるがこれも高度な隠喩と言え なくもない。第一句集は、作者の若いころの背伸びによるアカデミズムが青臭くもういういしい。
断崖のごとくに涅槃図を仰ぐ
- 涅槃図の大きな巻物を小さな自分が見上げている。測り知れない精神世界を畏れをもって眺めているのだ。
断崖のようだった。と、これは直喩。レトリックを意識的に使おうと涙ぐましい努力だ。30年ほど前、俳句に興味
を持つ若者はごく少なく、青年作家特集が組めるのは波多野爽波率いるところの「青」と能村登四朗率いる「沖」
位しかないと言われていた。他結社では1~2人いたらそれはもう若いというだけで甘やかされて育ったという。
爽波没後解散するまで「青」で切磋琢磨し鍛錬を続けたようだ。記念の第一句集は完成度が高い。
「冬の空朝礼台のぐらつきぬ」 「紫陽花の毬に抽斗開けてある」
「風花の毛鉤に触れて消えにけり」 「何を以て心埋めむ落葉籠」
「朝市女茄子苗売れば笛も売る」「涼しさよ熊手の先の焦げてゐる」
「じつとしてゐても大簗ぐらぐらと」 「大文字のばらばらと火の欠けてゆく」
(第一句集「浮巣」昭和63年7月牧羊社) - (H23年2月18日)松永 典子
花のあとさき風吹きて道祖神
- 飯田龍太の「雲母」と「青樹」に学ぶ。8年で同人「雲母賞」など、目覚しい活躍。その後長谷川双魚と結婚、死別、「青樹」主宰。とドラマチックな人生だ。12年で第一句集「方円」その後、さらに8年をへてこの「水辺」を出した。
花を詠むのは難しい。真っ向から立ち向かうと花その物の生命力と神秘性に負けてしまう。だから、花衣ぬぐやまつはる紐いろいろ(久女)等一句一章の句でも少しずらした秀句が多い。これもあとさきとややずらしぎみだが、花の持つ経過時間の要素をうまく取り入れ、金輪際動かない道祖神を詠んで成功している。静かなものと動的な散る花のイメージを取り合わせ、これは案外正攻法のようでいて、「あとさき」の言葉の発見なのかもしれない。 花冷の箒さかさに日暮れけり
- 箒がさかさに干してあったというだけの風景なのだが花冷えのなかで日暮れていった静謐な、これも時間が主役なのか。ドラマチックな道を生きている人の持つ時間は格別なのだろうか。 (第二句集「水辺」牧羊社)
- (H15年4月10日)松永 典子
寝に帰る鳥つぎつぎに雪涅槃
- 陰暦二月十五日は釈迦入滅の日で、各寺院では涅槃図を掲げ、涅槃会を催す。常楽会。塒へ急ぐ鳥を見ている作者。一日雪。つぎつぎにが何事かが起こっているのではとの大いなる不安を現している。父祖よりの地で農業を心をこめて続けている。それ故に季節に、より敏感な生活周期となっていて、表面だけなでたような句が多い中、自然に向き合う臨場感が一味違う。
切り藁を箕よりうばへり雪解風
- 箕は穀類をあおって殻・塵などを分け除く農具。竹、藤、桜などの皮を編んで作る。(和名抄)
切り藁は藁を切って束ねた物や藁たわしのことをいう。だから何かに使用したあと、軽くすすいでそれを洗った藁たわしも箕の中に入れ、その辺においていた様子だろう。それを雪解の風がうばっていったというのである。春になる気分がよく表れていて、あーあ、まだ使うんだったのに、ま、いいか、又作ればいいやと、何にでも前向きに考えられる待春の心が、読者の心もウキウキさせてくれる。他に「野良着きておのれに戻る竜の玉」など。(第一句集「春の畦」鳰書房)
- (H15年2月1日)松永 典子
にんげんは悲しみの泡夕おぼろ - この句を読んだ時、少なからず衝撃をうけた。初学の頃、無邪気に楽しく作句をしていたので、こん なに深い句が可能だとは思ってもみなかったのである。楽しい、悲しい、美しいなどの説明的になる言葉は、 なるべく使ってはいけないと、諸先輩から言われていた。今でもそれは有益と思っている。 すべて心得た上での、技術を超えた止むに止まれぬ内容の時は、前後の言葉に細心の気配りをして一句を成すと、 こんなに深い句になる。名詞にするか、形容詞にするか、リズムはどうか、動詞の多用はないか等。その他、 文法に厳しく、文語の語法の質問にも丁寧に答てくれた。馬酔木の主要同人としての仕事の傍ら、沖の編集長 として確たる地位を築き、主宰の能村登四郎と共に「沖」の基礎を作った師、林翔ならではの句と思う。
石笛に相模の小野の野焼きかな - 石笛とは、太古の信仰乃至呪術に用いられたとされる原始的な楽器の事である。現代の音楽家が
当時の音色を再現して、その素朴な音を甦らせたとある。原始も仲間と火や音で通信し、連絡をとったり、
生きる孤独をなぐさめ、傷ついた心を癒し合ったりしたのであろう。古代人に思いを馳せ、太古も野焼きを
しながら家族と暮し、社会を作っていったのだと想像する。災害で助け合ったり、家族や仲間をを大事に、
生きようとするそのひたむきさに打たれる。心の中は現代もあまり変わっていないかもしれない。火は人間の
血の自覚や、無意識の、遠い記憶等を呼び覚ましてくれる。
昨今の軽く軽くという 方向も、悪くはないが、真正面から取り組む正統な句を作るには、相当な力が要る。時間と鍛錬が要る。 私も含めてそれらから逃げているのでなければいいのだが・・・。
「月徐々に射す凍て滝の苦悶相」「滝凍つとはげしく星の息づけり」 「さっと研ぐ男の利鎌あやめ咲く」「雲をシュークリームにして初凪す」「水尾はすぐ蓴がとざし蓴舟」 「石笛の天より鳥の交み落つ」「ビバルディー「春」息子に来たる女客」「岬端の空早縫ひに赤蜻蛉」(第三句集「石笛」牧羊社) - (H16年1月13日)松永 典子
蕗の薹らしくなくなりかけてをり
- まっさきに春を感じるのが芹や蕗の薹である。根茎から生え出る花茎。別名ふきのじいともふきの しゅうとめとも。便秘やせき止めにも効くらしい。ほろ苦い味が魅力。長けてくるともうもやもやになって 別のものに変わろうという意思さえ感じる。その曖昧な時期の蕗の薹である。らしくないというところに俳 味を感じているのだ。近松の「虚実皮膜」とは事実と虚構との中間に芸術の真実があると。間は間(ま)。曖 昧なもののよろしさもある。
シクラメン炎の裏を見せてをり
- 真綿色したシクラメンほど清しいものはない♪と、小椋圭は言った。松永氏は炎の裏という。その
形状を炎というからには赤いシクラメンか。白かもしれない。比喩がぴたりとはまった時の爽快感。
同 姓の氏とは随分昔に埼玉文芸という雑誌で出会っていたらしい。お便りを頂いてまだ学生だった頃の氏の名 を隣に見ていたからわかった。私の方は俳名を史子から典子に変えていたので、別人と思われたのだろう。 第一句集の中で句に詠まれた娘さんの名が典子(のりこ)さんだという。年鑑で隣り合っていたのでとお便り を下さった。今は中学校の先生で、第三句集「げんげ」で俳人協会新人賞を受賞し、とても充実した仕事をさ れている由、俳縁の不思議さを思う。「浮野」同人。
「妻抱くは胎動を抱く冬紅葉」 「雪片に刺さるる山のしじまかな」 「嬰児にこの世見え出す木の芽晴れ」 「裸子を抱きて松葉の匂ひかな」 「夕焼のすぼまる野辺の ひとところ」 「登山靴がぼがぼ駅を出で行きぬ」 「年の瀬の臼に使はれ馬鹿力」 「さるすべり産声高く上げにけり」 (第2句集「肩車」平成5年5月牧羊社) - (H22年1月12日)松永 典子