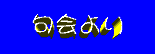あざ蓉子
- 愛人を水鳥にして帰るかな
- あざ蓉子らしい句だ。力強く、セクシー。愛人というからには、もうすでに、恋の駆け引き段階
(アプローチがあり、告白があり、折衝があり、コンセンサスがあり、コンタクトがあり、という)
は過ぎて周辺はどうであれ安定した関係である。
初めは双方の情熱も同量であっただろう。いや自分の方が熱心だったかも知れない。 関係がクライマックスから安定に向かう時、男と女では、微妙に違う。
もし、温度差が激しい女だったら、もうとっくに醒めている自分を自覚しているだろうし、 それでも安定の温もりは心地よいだろう。 この場合「帰るかな」であって「帰すかな」ではない。奪い取った愛であるなら、後者の期間があったに違いない。 でも今は水鳥になった愛人を置いて帰るのである。そう仕向けたのは自分。でも何かが違うような気がする。 幸福な退屈。それとも・・。(第三句集「猿楽」) - (H13年11月20)松永典子
シーソーの一方を地に着けて冬
- この人の冬の句はピカイチだと思う。感性もさることながら、物で深い事が言えるのだ という事を最初に教えてくれた句群である。20代だった作者。まだ独り身だったのだろう。 一人も子供がいない公園は、遊具も淋しげである。一方を地につけているという何でもない事の 発見が、この人の孤独な心象風景も映しているようである。写生とは心眼を磨くことか。見ただけ では断じてない。
消し忘れ来し寒灯に待たれをり
- この句を読むとやっぱり独り身らしいとわかる。これほどのわびしさがあろうか。
前の晩から点いていた門灯だろうか、朝出るとき消し忘れていたのだ。それでも真っ暗な中
を帰るのはもっとわびしい。もしかしたら、心の隅に、灯を点けて待っていてくれる人を切望
するあまりの無意識の点けっぱなしだったのかもしれない。
十分な力を持ちながら、あまり評論などを書かない潔さがあり、一部の人からはどうも 消極的と見られがちだったものの、こうしてよい作品は時間がたっても人の心に残る。それ自体 が時間の砂に埋もれるのを拒否する、そういう作品を作りたいものだ。シャイな性格もあろうが、 私は、むしろ彼の静かなプライドではなかったかと思っている。 (第一句集「二水」牧羊社)
- (H14年12月7日)松永 典子
- しろがねの空気すらりと葱の中
- かつて”沖”で史子という俳名で勉強していた頃、眩しい先輩達の中に上谷氏がいた。
コピーライター、グラフィックデザイナーとして、措辞の完成度の高かった氏は虚実論争に於いて、 虚は写生の中にあるというパラドックスを堂々打ち立てた。
近松門左衛門の「難波土産」に「虚実皮膜」 と言う語がある。芸は実と虚との皮膜の間にあるということ。事実と虚構との中間に芸術の真実があるとする論。 (広辞苑)
葱の中にすらりとした空気がおさまっているという。それもしろがねの。 葱の形態とそのみずみずしさへの絶賛である。この小さな造化の妙を見据える内に、生の不可思議とか 人智の及ばない何者かを見たのであろう。そしてそれに相対する人へのあたたかい視線。
- 蛇口より曳き出す寒の水一本
- 蛇口を一杯に開いて水を放出している。雪を溶かしてでもいるのだろうか。それともバケツに勢いよく
溜めている情景か。いずれにしろ外の蛇口のような気がする。寒さで、蒸気が上がっているのが見える。一本
の水をひきだしているのだと捉えた。独自の発見のように見えるが、これも単なる写生とは言い難い。
どこかとぼけた味もある。
力量のある作者が、現実との葛藤と戦い続けた22年間の、絞りに絞った第一句集「登高」は白眉である。
(第一句集「登高」)
- (H14年1月20日)松永 典子
- 高空に水あるごとし青鷹
- 青鷹と書いて「もろがへり」と読み、生後三歳の鷹をいう。きぃーんと冷え切った高空に、精悍な青鷹。
水あるごとしで、ゆうゆうとした王者の威厳とゆとりが、鋭く厳しい美しさを際立たせ、 無限の詩的空間を作り出している。当時30代で三冊の詩集を持つ詩人が、 現代詩の荒涼とした極北への志向途上で出会った魂の慰籍が俳句だったという。
もともと萩原朔太郎の研究の過程で知り得た「与謝蕪村」への興味や、 日本詩の歴史的過程でどうしても係らざるをえなかった俳句は、 宿命の出合いとして均衡を保つに至り、俳句の伝承性、習俗性等も受け入れた上で新しい何かを模索。 単なる詩からの逃避組ではない。
- いつも陽の死角にありて浮寝鳥
- 日向争いを浮寝鳥もするのであろうか。それとも浮き寝の鳥の中でいつも影に追いやられる鳥がいるのか。
陽の死角とは自分の生存の位置とこの作者は言いたげだ。
もっとも生ぬるい場所なんてこっちからお断りでぇいと啖呵をきる面々もいる。
BS句会で2句とも人気句だった氏の作風が、あまり変わっていなかったのも嬉しかったと同時に安心もした。
自分の出会った詩形に愛着と自信を深め、着々と生存の位置を固めてゆくだろう。
(第一句集「青鷹」)
- (H13年12月20日)松永典子
年用意おもはぬ紐の役立てり
- 無意識にためていた何でもない紐が、大掃除などの年末の行事の際大いに役立った。生活の一齣
での、ちょっとした感懐。題名にもなった「高麗郷」は埼玉県の日高市高麗川一帯で、帰化した高麗人
の裔が住みついた土地柄。豊かな自然と歴史的に美田素封家が多い越生出身の作者は、クリスチャンの、
俳人でもある農事関連の実業家のご主人ともども、実に堅実に自然との関わりの濃い句作を続け現在に至って
いる。序文で、能村登四郎もその作風が女性に似合わぬ骨太で肉付きが豊かで、具象性が強く、事俳句を
越えてどこまでも物に即していることがよい。と手放しで誉めている。都会派の多い関東女流の中にあって
不足を嘆くのではなく、身の丈での身辺詠の見事さを具現させた手腕は立派というしかない。
敷藁に日がこんもりと雪のあと
- 作物の根元などに敷いた藁に、雪のあとの日が当っている。こんもりとは雪の量感であるが、
日差しそのものがこんもりという言葉を引き出した。そのほのぼのとした生き物へのいとおしさや、自然の
厳しさ深さは本当に自分の手で作物を作らなければ分からない感覚であろう。都会派の物欲しげな吟行句
との違いがよくわかるというもの。ある種うらやましい環境でもある。が、自然があるだけでは、俳句作家
になれるものではなく、やはり本人の努力と意欲が必要なのだろう。埼玉県に赴任していた頃たまたま近所
に住んでいて、とてもいい勉強をさせてもらった。謙虚な人柄とその大らかさは、すさまじい勉強に裏打ち
された強さでもあった。あれから30年にもなろうとしている。
「民話より米こぼれつぎ雪となる」「干大根しわしわ母の医者嫌ひ」「父母も田仕舞酒にすこし酔ふ」 「もう先を争はぬ水秋深む」「窯出しの種火のやうな烏瓜」 「眠り蚕へ戸を少し引き外出す」「日本海ぐるみの夏の切符かな」「営林署よりだしぬけに黒揚羽」 「蛍沢より飲食の水引けり」「左義長に消防署より一人くる」「着替へても早乙女水の香をまとふ」 「明日は刈る田へ月光のすき透る」「手の枡のほぼ確かなり新小豆」(第一句集「高麗郷」牧羊社平成2年)
- (H16年11月6日)松永 典子
靴底のななめに減りぬ賞与月
- 若いサラリーマンの溜め息が聞こえる。12月という月を、師走でもなく年の暮でもなく賞与月と 表現した。靴底は斜めに減っているのだ。多忙である事に加え、薄給でのつましい暮しの中から靴一つ 新調するのにも、タイミングを考えざるをえない。自分の暮しの中から何気ない事象をとりあげて きっちりと表現すると、このようなペーソスとなる。派手さはないが、しっかりと地に足をつけた市井の 健気なくらしの、片頬くらいの笑いと自嘲に対し、同じ目線で共感する事ができる。
冬林檎かじり未完の設計図
- 長身ですらりとしたキャリアウーマン。静かで知的な印象を受ける作者は、南画を嗜む祖父を
敬愛していたり、自身でも絵画、音楽、映画と良質な芸術作品に造詣が深い。30代後半。本格的に俳句結社
に入門してまだ15年しかたっていないが、基本をしっかりと身に付けていて、今後楽しみな作家である。
破格な「吾」を出す事にこれからの課題があるのかもしれない。
「南風」同人。
「初蚊帳のすこしすつぱき香に寝たり」 「たくさんの吾が生まるるしゃぼん玉」「受験子の寄れば鋼のにほひせり」「大橋を霞の国へ渡しけり」 「子燕の母呼ぶ頸の抜けさうな」「噴水の落ちゆく快楽ありにけり」「稲妻やふたりの距離の縮まらぬ」 「正論にひそかに耐へし夜長かな」「山蟻に雫のやうな眼のありき」
(第一句集「和音」平成18年7月文学の森) - (H18年10月30日)松永 典子
讃美歌の余韻咳なほ堪へてをり
- 讃美歌のあとの清清しい余韻が続いている。そこにいる聖歌隊、神父様、信者の善男善女、 ステンドグラス、マリア像、清浄な空気、全てのものが、いま崇高な精神の塊となって光に満ちている。 その中にあって、この作者はその少し前から、咳が出そうになっているのだが、顔を真っ赤にして、出さない よう堪えているのだ。その一瞬の緊張感が伝わってくる。人の精神の崇さと、生きている故のどうしようも ない生理作用にひそかに格闘している作者の悲しくもおかしい場面は、誰しも経験するのではないだろうか。 長い間、教職にあった人らしい気遣いは今でも通用すると信じたい。
火星に異変あるとも餅を食べて寝る
- この句、昭和34年の第一句集「礼拝」(らいはい)に出てくる。その頃に火星が月に近づいたのか
、それとも火星蝕等の天体イベントがあったのか、「水」が見つかったのだったか。いづれにしろ
世間はその話題でわくわくしていたのだろう。そんな事にもお構いなく日本人の自分は餅を食って寝る
のだという句。この人の持つおちゃめな一面が端的にあらわれていて、誰にも愛される明るさと
素直さが、いい具合に句に結実した。「知」と「愛」併せ持った俳人だと思う。
「圭」主宰。
「虹二重神も恋愛したまへり」 「交響曲の最後は梅雨が降りつつむ」「木漏れ日の斑を総身に怠けをり」「礼拝に落葉踏む音遅れて着く」 「狡る休みせし吾をげんげ田に許す」「りんご採り尽すまで樹の上にゐる」「子育ての乳房ひきしめ猟の犬」 「青春を浪費せるシュプールの深さ」「雪を待つのみ山畑の無一物」 (第一句集「礼拝」昭和34年近藤書店) - (H18年12月10日)松永 典子
獅子舞の開けたる口の中見えて
- 最近、都会では辻に現れる獅子舞は、めったにいなくなった。イベントや祭の余興の一つとしてか、
地方の行事の中でもメジャーなものになりつつある。メディアに現れたり、獅子頭が博物館に保存されてい
たりする。舞い手が高齢化したり、少なくなってきたのかもしれない。我々の子供時代には、
遊び道具が限られていた変わりに正月ともなると、商家や表通りの家々の玄関にまできて舞った。
子供達は珍しがったり恐がったり。お正月の風物として気分がうきうきしたものだった。
「童子」という俳誌を主宰している辻桃子さんは、 ほんとうに童女のような好奇心をお持ちの俳人である。普通だったら、舞そのものを見て、面白がる ところだが、その口の中が見えたという事の、興奮をいう。詩集も出す詩人だった。その他著書多数。 枯菊を焚いて焔をつくりけり
- これも主体はもちろん作者なのだが、枯菊を焚いたという報告ではなく、焔をつくったのだ。と、
それも枯菊の特別な焔なのだと。いかにも桃子さんらしい感性で、視点は並ではない。子供というのは、
可愛らしいだけではなく、時に、残酷な事象を乾いた感情で、捉えていたりするものだ。それは創造主の
ひたむきな視点に近いのだろう。
横浜生まれ。俳句を始めて21年目に第一句集「桃」を出した。転勤先の青森が気に入って永住すると いう。きーんとした潔い寒さの好きな俳人らしい。
「太宰忌の黒く大きな傘に入る」「雛の夜の磨り減らしたる下ろし金」「虚子の忌の大浴場に泳ぐなり 」「羽抜鳥みる逢曳きの見られをり」「あとかたもなく燃え果てし桜榾」「凍て瀧へ傾く父についてゆく」 「枯蓮の茎の出でたる泥を見て」「わが声のわれを出でゆく薄氷」「氷上のまつしぐらなる轍かな」 「寒竹の太きを跨ぎ母捨てむ」(第一句集「桃」昭和59年牧羊社) - (H17年11月4日)松永 典子
- 足首を入れて立つ足袋親鸞忌
- 報恩謝徳のために、11月28日の忌日に大法要が行われる。もはや一般的になっているので、季感はうすい。この場合季語の足袋がいい小道具になっていると同時に親鸞忌の邪魔にならない実に巧みな配合となっている。足首を入れないと立たないのだとの独自の発見もある。人がいてこそという深みへも通じるか。
昼の火事すりこぎ握ってゐたりけり
- サイレンを聞くと、何をしていても気になるものである。どこだろう、自宅は大丈夫だろうかと。
この場合は、自宅にいる主婦で、近所に火事騒ぎがあったのだろうか。幸いボヤですんだようだ。ふと気がつくとすりこぎを握ったまま家を飛び出していたのだった。日常のふとした心の動き。俳句はどこででもできる。しかし簡単そうに見える俳句ほど、難しい。それに気付くのにはある程度の下積みがいる。師の鈴木鷹夫は過去の累積された土壌の上に、ほんの僅かでいいから新鮮な花を咲かせようとする営為なのだと、ある日突然に新しい俳句ができるものではない事を力説している。能村登四郎、鈴木鷹夫に出会っていなければ、ただのお調子者だった私も粛然となる。
他に「なまはげの股間を猫の通りけり」「福助のお辞儀は永遠に雪が降る」「冬の蠅ときどき姉を好きになる」 (第一句集「鼬の姉妹」本阿弥)
- (H14年11月9日)松永 典子
降る雪を仰げば昇天する如し
- 普遍的な句である。降ってくる雪を仰ぎ見ると自分の方が天に昇ってゆくようだ。この作者の句は
難解で、なかなか理解できないものと頭から決め付けている人も多い。高柳重信に師事して師を見送った
経緯から確かにそんな傾向はある。俳句は座の文学。鑑賞者にも解り易く言葉の斡旋を工夫しなければなら
ない。それに季語等で季節をはっきりさせるという、決まり事以上の重要な約束があるが、月並みに堕しな
い為にも懸命な自己革新に腐心し、無季や破調の句も多い。それなりの配置や詩語への心配りがある。
それを充分解った上で、この初期ののびやかな詠み振りはどうだ。自由になろう、約束事の枷から逃れて 自在な境地を開こうと格闘する事もまた不自由な事なのではなかったかとつい凡庸な私は思ってしまう。 なまぐさき雨・雪・雨や翌檜
- 実は「翌檜」に「あすはひのき」とルビが振ってある。これがどうもわからない。あすなろう
だったら、一般的だし、読む人が勝手に解釈してくれるものだ。天才には自分だけの拘りがあって、どうで
もこうでなくてはと、自身を規定したがるし、そのこだわりが素敵だったりもする。しかし俳句の場合は
凡庸さも力になる事があるのだ。「千年の留守に瀑布を掛けておく」というその後の大好きな句があるが、
天才には周りが愚かに見えすぎて読む人を信じない傾向があるのだろうか。これは捨てた方がいいのでは
ないかと思われる句まで発表してしまっていると思うのだが。でもそんな何かが人の心を打つのかも知れ
ない。
「揚花火死後は棘出す人柱」 「屋上の墓石売場を飛ぶ電波」 「青空を吸ひ込み蝉の穴は消ゆ」「泳ぐかなからくれなゐの形代と」 「つくつく法師を握れる人柱となれり」 「禿山を転がる金剛力の蛇」「天地無用のビルにて蟹が茹で上がる 」「還りくる魂か1匁の花か」「村村の夏の鳥居を抱くなり」「水際に蛇紋を纏ふ母を見き」 (第1句集「猟常記」昭和58年2月静地社) - (H20年11月11日)松永 典子
ひとりでに扉があき雪の街に出る
- 自動ドアが当たり前になりはじめた昭和末期から平成にかけての作。当たり前の事を当たり前
と通り過ぎることなく多作し、その中のほんの一握りの成功作をさらに絞り込んで発表する。ひとりでに扉が
開いて雪の街にすぐに出られる時代に、老人となった自分が戸惑いながら生きているのだ、ドラエもんの
どこでもドアのように。というぐらいの句意か。
私はこの句に登四郎のお茶目な一面を読み取る。 取っ付きにくい風貌からはとても想像ができない一面だから、とてもチャーミング。 「なぜここにいるか不思議な花筵」や「逝く年の軽石と湯に浮かびをり」等に繋がってゆく部分だ。そんな とぼけた自分をしっかりと見ているもう一人の自分がいる。
葱畑の暮色や通夜に早過ぎて
- そんなに親しい間がらでもないが、お付き合いでどうしても顔をださなければならない通夜だった
のだろう。落ち度のないよう時間を見計らって行ったが、ちょっと早過ぎたらしい。夕暮れの葱畑でも
見ながら時間つぶしをしようかとうろうろしている老紳士の姿が彷彿としてアイロニーを感じさせる。
それと対照的な「豊頬や若さを余す寒の死者」は、もっとも期待していた福永耕二の突然の死を嘆いて
作った句で、これはもっと切羽詰った感情の発露が顕著な、別の通夜の句である。
死者との関係や気分が一読してわかるには過不足のない措辞が必要で、その上に凡にならない表現となると
相当の力量が要るだろう。面白い句も楽しい句もいいし、純朴な句、観念の句などいろいろあっていいが、
自家撞着や、わからない句はいけない。人は自分に甘いという特徴があり、それを諌めるための句会でも
ある。人気があっても、俗に陥り過ぎたり分かりすぎるのは、詩としての緊張感がない。反対に詩を強調し
過ぎると痩せてきて別の月並みになる。もっとうまい句がどこかに有ったりする。その為の選句眼をもった
主宰が必要となる所以だ。その上での冒険が要る。昔の人が積み上げてきてより洗練された方法が具体的で
優れているのは、鍛錬しながら楽しめる事で、無記名で誰でも参加できるように工夫されているところに
有る。登四郎はそれを坦々とがんこにしかもおおらかに信頼していた。同じ土俵でなくてはならないと。
「鳰みるといふことにして家を出づ」「にほどりの浮かび上がりしきょろきょろ眼」 「ひとつづつ開きて梅の反り睫毛」「みどり児がゐておろおろと桜過ぐ」「曼珠沙華跨いでふぐり赫とせり」 「なまぬるき慈雨ひとしきり地蔵盆」「二十重なる枯蔓くぐり出て男」「切り口に泡ふつふつと榾火かな」 (第七句集「冬の音楽」永田書房) - (H15年11月14日)松永 典子
冬耕の母に近づく道あらず
- 母堂没後の句。父亡き後も農業をしながら作者を慈しみ育ててくれた母。今でも冬の田を見ると
母に会えそうな気がしてつい出てきてしまう。
作者には母の冬耕の姿が見えたのだろう。しかし、 それに近づく道が見つからないのだ。 湯豆腐のことことと情動くなり
- 湯豆腐はもっとも心をなごませてくれる家庭料理だと思うが、料亭などで小さな集まりの旧交を
あたためたりするのにもほどよい舞台装置であり小道具でもある。自ずから人間関係の修復等にも
役に立とうというものだ。もっと想像を膨らませると、いろんな意味でのイケナイ関係だったりもして。
序文で能村登四郎は、「句会で点を稼いだり、高点になる型の作家ではない。どっしりとして、 ものの本核を掴んでいく作家だと思っている。若い時に才智をひらめかせる人は、すぐ色褪せてしまうが、 波戸岡さんはこの先もっと大きな力の出せる人だと思っている。」と記している。大器は晩成するもの だと、晩成の大家が言っているのだ。俳句に必要なのは瞬発力だけではなく、それに加えてマラソンの ような持続力も要るのだ。堪え性のない若者を繋ぎとめるのに汲汲としないで、誰にでもある山坂を 坦々と歩く者の中にきらりと光る非凡さを認める。15年前のカリスマの予見であり達見であった。因島市 出身。国文学者。
「枯れといふ身軽さ海になかりけり」「夜食とる大きな頭ばかりなり」「耕して島は天頂まで潮騒」 「虹の根にもっとも濡れて母の島」「下り立ちて父なき島の油照り」「口紅を落して妻もおぼろめく」 (第一句集「父の島」ふらんす堂)
- (H15年10月7日)松永 典子