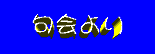進級し大人のカレーライスなり
- 小学生の進級らしい。それも3・4年のギャングエイジと呼ばれるやんちゃ盛りの男の子。大人の仕草を 何でも真似て虚勢を張る。この時期の一年は充実して長い。自分ももうガキじゃねぇんだ。 カレーは甘口りんご蜂蜜味ではなく、大辛のディナー用にしてと母に注文。始めての味は冷や汗もので食べた。 満足したが、今度から中辛にしようと密かに思う。大人の味は、痩せ我慢の味。父の目にはほろ苦く映った子供 の成長であったろう。
吸呑の中の新茶の色なりし
- 回復に向かって気分が楽になった。透き通った吸呑に新茶の色と香りがゆれている。普段はただおい
しいなぁと小さな幸せをかみしめるが、病状が快方に向かうときの新茶は命そのものを身に通すようだ。視点
の新しさと着眼点のユニークさ、幅広さで圧倒。「青」「沖」で青年作家として活躍、のち「銀化」。伝統と
は爽波の言っている多読多憶ではないかと。季語の斡旋の仕方、二句一章の形式を徹底的に学び取った。
「毛虫焼く就職情報誌が火種」「西瓜ひとつ朝礼台に置いてある」「職務規定ありて衣を更へにけり」等。
(猫舌)
- (H15年5月4日)松永 典子
関取がすててこでゐる地方場所
- 相撲は武技のひとつで、古くから宮中では陰暦7月に行われたことで、俳句では秋季とされる。いま
では、それぞれの季節で、地方場所も盛ん。
くわい型に髪を結った大きな体躯で、宿泊先の夕涼みなど 楽しんでいるのか。まだ駆け出しでもすぐに相撲取りとわかり、散歩中の人々の好奇の目を集めてしまう。 最近ではキングサイズのものもいろいろとあるが、やはり着易いステテコが一番とは、一般人も一緒かなと。 (冬麗)
- (H14年8月25日)松永 典子
音楽を耳に差し込み雲の峰
- 好きな色に髪を染めた若者。海辺で、一休みしている時もウォークマンから流れる音楽を聴いている。
胸に金のネックチェーン。それともプールの監視員で、高い所から人々の安全に気を配っているところか。
どんな時にも音楽と共にある若者の形態を捉えた。音楽を耳に差し込むという表現で、イヤホーンの中の孤独 な楽しみの様子が分る。一応辺りに気を配っているようだが、しゃかしゃかと漏れ出る音が気障りな大人は、側 を通る時ちょっと離れ気味になる。
雲の峰という大きな季語が全てを包んでいる。
- われよりも子の毛脛濃し祭鱧>
- 最愛の妻を看取りの後亡くしてしまった作者は、息子と二人、祭の遠音を聞きながら鱧料理を味わって
いる。ふと見ると、胡座をかいている息子の毛脛は自分より濃い。自分も歳を取った。普段は口に出しては言わ
ないが、頼もしくなったもんだ。
職場句会から始まった作句歴は長いが、仕事の関係での中断がかなりあ る。本腰を入れたのは、能村登四郎に入門、選を受けてから。とびっきりの名文を書く。コツコツと俳句に関わ った時間を、誠実に大事に研鑚していた事がわかる。ふけとしこ等と結社誌「青麦」を主宰。「衣紋竹にぞろりと 掛けて私生活」感覚もさることながら、ゆったりとした人事句が持ち味。ほっとする。その影には、厳しい鍛錬 があった事も忘れてはならないだろう。(私生活)
- (H14年6月17日)松永 典子
- 橋脚に潮のよごれ花蜜柑
- 端正なこの句などは、この作者の独壇場のように見える。
香川県出身、新聞記者。知性派で、努力家。と言えば肯けるか。
四国出身者でなくとも、この光景は日本の心のふるさとだ。
花蜜柑の何と可憐にぴたりと決まっている事か。
興味の対象に接近するのに、少年のこころを持ち、かといって情に流され過ぎない適度な距離もある。(青垣) - (H13年10月29日)松永典子
夏霧の山男にも乳首あり
- 「夏霧の」で軽く切れている。山男にも乳首があるとは、事実ではあるのだが、なかなか意識 する事はない。ただの乳首であったら、母のそれで、そばに赤ん坊がいたりする。それ以外だとしても せいぜいがセクシーな女性を思い浮かべるくらいだろう。いずれにしろ女性という事が共有のイメージ となる。俳句は短いので、そこまでの共通認識は言わなくても判る部分として説明はしない。それが 男の、それも、いかつい山男のそれだというのだ。そこのところのずれの面白さがこの句の眼目。夏霧の湿り ぐあいと、冬山の危険さともちがう心安さとがよく付いていて、結構女々しいところもあるのだよと、言外の 意図が伝わる。
おくり名は海にあふれむけしの花
- 諡は人の死後に、その徳をたたえて贈る称号のことで、諱(いみな)。
氏は戦後生まれの団塊の世代である。戦争の実態は知らないが、子供心にも苦労して育てられて
いた事を、親の後姿から感じていた。
海に沈んだ英霊達の、子供を成せなかった無念さを、生き残ったもの 達はどう心に 落したものか、あるいは、この世の方も果てしない地獄であるのだよといわんばかりに、芥子の花が風に戦いで いるといったところか。
芥子は源氏物語では護摩に焚いた記述がある。その種の小さいことから微小な ことにたとえられたりもする。
学生の頃、「夏草」「鷹」に拠るも、高柳重信から自由に作ってごらんと囁かれたという。結局、 俳句形式が持っている知恵が書かせた句が残り、シュールレアリスティックに書くには自ずと限界があると、 有季に復する事に決め、現在「豈」、「天為」編集長。
「炎昼の垣根を黒く塗りて曲がる」「眠さうな眼の奥にゐる曼珠沙華 」「居酒屋に棲む広重とあめふらし」「サロメ忌の鳩尾うつす青鏡」「戦争や昆布のにほふ零がある」 「夜あそびの夜長をを過ぎし田唄かな」(第一句集「繍鸞」昭和57年8月鳥火屋文庫) - (H18年6月1日)松永 典子
ひかえめな自画像に倦む遠蛙
- 若い頃に憧れていた女流の一人である。さっぱりとして自立した女性のひかえめともいえる自画像 に自分で飽きてしまったという句。三十数年前の俳壇は女流の台頭著しく、百花繚乱の様相を呈していた。 現在はそれが当り前で、もう誰もわざわざ女流と冠したりはしなくなったが、その頃は男性の俳人と肩を並 べようとみんな必死で勉強していた。功名心も勇み足もありとあらゆる自己研鑚が自己顕示欲と重なり、 もの凄い事になっていたが、一部の実力者には、彼女の様に政治的かつ器用な売り込みからは遠い処で冷静 に研鑚を積む人もいた。出し抜いたり出し抜かれたりの喧騒は遠蛙のようだが、少し厭きてはいたけれども、 それが自分の生き方だと肯っていたのだろう。俳人は俳句で勝負すればいいと。
したたかの汗いさぎよき離婚歴
- 「プール帰りの子が来て書塾しづまらず」という句があとへ続くが、それ以後は書家として、書
塾を開かれていたらしい。「夫に拠るのみのたつきの豆を撒く」が冒頭近くに置いてある。実生活を赤裸々
に詠んで憚らない気風のよさも江戸っ子の粋に繋がっている。背筋を伸ばして生きる姿勢自体がこの句集の
魅力にもなっているし、題名の「雨後新秋」は象徴的で印象深い。
「枇杷咲くや忘れられゐし小さき借」 「負ひ目なく生き来て冬芽いさぎよし」
「マフラーのうすき体温するりと抜く」 「かなもじの自在こころに野火走り」
「狂ふとは一瞬のこと花ざくろ」 「調子下げて寒明くる夜の三の糸」 「畳まれし蚊帳の重さも旧家にて」
「涅槃西風陶土が畑の裾よごす」 「ひつそりと春立つ犬のさぶ死んで」 (第1句集「雨後新秋」昭和56年東京美術) - (H22年4月13日)松永 典子
日盛や剥落しつつ蝶が飛ぶ
- 日盛りの蝶はそれだけでもなにか異次元的。剥落しつつ飛ぶと捉えた視点が卓抜である。ハイス ピードカメラで捉えたような時空を超えた存在としての蝶。夏の蝶は大振りで、いきなり人の視界に入って くるので、美しいと思う前に正体の分らない不気味さ感が先立つ。空間が剥落しているのか、蝶が剥落して いるのか。
手がありて鉄棒つかむ原爆忌
- 手の存在が命の存在を象徴している。具体化していると言った方がいいのかもしれない。原爆忌
の句はなかなか扱いに困るが、さらりとした言葉と具体的なイメージが、人類全体の問題提起という大き
な(大袈裟にもなるから厄介)テーマを破綻なく表現できるのだろうか。
この作者の句は夏の句に いい句が多い。日盛、原爆忌、ひまわりと激しい季語に片寄っている。個性的な現代女性の像が浮かぶ。 「鷹」同人。
「甲板のひろびろとして旱かな」 「卓袱台に西日たださす家なりし」 「万有引力あり馬鈴薯にくぼみあり」
「封筒の密なる白さ原爆 忌」「蓑虫にヘリコプターの降下音」
「物置に箒が威張りクリスマス」 「千人の着席の音梅雨深し」 (第2句集「縄文」平成17年3月ふらんす堂) - (H21年5月5日)松永 典子
見覚えのなきハンカチを洗濯す
- 夫だろうか息子だろうか。ポケットから出てきた買った覚えのないハンカチ。腑に落ちないままに 一緒に洗濯した。洗濯機の渦を見ながら、しばらく心の波立ちがおさまらない。干す時にぱんぱんと皺を 伸ばしてまた少し考える。こうした日常の中の心理の動きをハンカチという小道具で仕立てる。俳句の醍 醐味でもある。
羅のひとに尋ねし船厠
- どの人に尋ねてもよさそうなものだが、人は物を尋ねるのにもちょっとした選択をしているという
。彼女は乗り合わせた時から気になっていた、羅をすてきに着こなしている人に聞いたのだ。家事も仕事
も立派にこなし華美なところの微塵も無いさっぱりとした実力派女流俳人もどこかに女性らしいあこがれ
を持っているものだなぁとちょっとうれしくなった。日常からの素材をとてもうまく俳句にできる力は
うらやましくもある。主宰の近くに住めることも。しばらく月4回の句会の内の東京句会に欠席投句を
お願いしてもらっていた。「沖」同人。
「湯ざめしてやうやく己がことと知る」 「甚平で出てくるまでの間がありぬ」 「遠足のしっぽ校門出るところ」
「秋草を一つ知りたる旅で よし」「祭帯解くするすると何か失せ」
「グッピーの水音雨と入れ替り」 「椅子よりも正座雪降りさうな日は」 「凍滝にかうも黙殺されゐたり」
「くちなしに錆色禁句おもひ出づ」「座ること無き暮しにも小鳥来る」 (第1句集「普段着」平成3年6月牧羊社) - (H21年4月19日)松永 典子
河骨にどすんと鯉の頭かな
- 黄色い河骨が浅いところに咲いている。そのしずかな風景にもっと近寄って根元の水面を見ると、 まるまると太った鯉が2~3匹悠然と泳いでいる。その内の一匹が頭を河骨の茎にぶつけたのが見えた。 別に音はしなかったが、どすんとぶつかったような量感だった。分かり易い取り合わせだが、どすんの オノマトペアが的確な擬態語に近い表現となってこの句を面白くしている。河骨と鯉の存在がぶつかった 時の思わぬ心の動きが目に見えるようだ。
月明の蚊帳吊草の下は崖
- 学生俳句から「渦」「青」を経て、「天為」「屋根」で活躍。礼儀正しい好青年で、句柄も端正
にしてスリルに満ちている。この句、家路からはまだ遠く、月夜があまりにも美しいので、少し車を降りて
休憩しようかと家族か友人などと深呼吸をした。見ると蚊帳吊草が月明にすうっとのびていい雰囲気であ
る。どこまでも続くユートピアのようだったのに、近づくとその下は崖であった。よきパパよき社会人で
もある。
「金網に吹きつけらるる野菊かな」「冬空へ出てはっきりと蚊のかたち」「ぼんやりと紫陽花のある 障子かな」 「風邪の目に竹かつがれてゆくが見え」「火の中に見えて紫式部の実」「なきがらの四方刈田となつてゐし」 「こまやかに木賊吹かるる雪解かな」「つばくろや草を擦りつつ舟のゆく」「瓜番の二の腕に蛾の止まり たる」「鶏吊つて南天の実の大粒に」「草むらにトマト散らばる野分かな」(第一句集「鶏頭」昭和61年牧羊社) - (H17年7月24日)松永 典子
青谿の次のページへ急カーブ
- 昭和53年の作。山添いの道路をドライブしているのだろう。あるいは、鉄道の窓側の席に頬杖をついて 見入っているのか。「わけいってももわけいっても青い山」の季節だ。 似たような景色が延々と続くが、ひとつとして同じ表情の場所はない。新鮮な空気、みどりの光、うっとりと 見ているうちに、急カーブで次の谿にさしかかる。絵本のページを開いていくようだ。阿蘇を通り熊本の正木浩一、 ゆう子兄妹を訪ねた時の作品。
酔の頭をぴろぴろ祭笛が越す
- 昭和23年馬酔木入門以来、鶴、沖と、人間探求派と呼ばれる秋桜子、波郷のもとで、じっくりと勉強を
してきた。第一句集「絵葉書」は数十年にも及ぶ登四郎、林翔との句縁の中での仕事を纏めた物である。そして
第二句集の「雨傘」を残し、50代後半で没した。俳句の世界では夭逝といってもいい年代であろう。常に新しい
物を目指していた。「絵葉書」では「あをあをと銀河がちかし初契り」「大小の雪降り吾子に言葉殖ゆ」「子を
死なせし顔秋風に吹かせけり」「枯芙蓉妻を笑はすまで喋り」と、過酷な運命を呪うことなく、自分は縁の下
の力持ちとして家庭を支え、「沖」を支えてきた。鈴木鷹夫と共に師と仰ぐ作家の一人である。無知な故に生意気
だったあの頃の自分を殴りたいと思う。しかしあの頃の自分も今の自分を殴ってやりたいのかも知れない。
「暑き鳩さらに一羽の加はりぬ」「燈台がちょんと頭を見せ曼珠沙華」「永劫に似て滴りの水時計」 「もう踊り来ぬ子よどこで輪を抜けし」「冬鵙に縞あたらしき横断路」 「懐炉ずれをり甘きもの妻へ買ふ」「大嚔して両眼の跳びちがひ」「コニャックに胃の腑が灯り花夕べ」「 ルカといふ耶蘇名を持ちて新社員」(第二句集「雨傘」東京美術) - (H16年6月3日)松永 典子
空を行く花びら五十寂しきか
- 博報堂のキャリアとして充実した仕事のかたわら学生時代からの句作を続けてきた。その間仕事
のための中断があったが、山口青邨に一から再入門したのが30歳。同時に「日本列島桜花巡礼」を発心。
それから13年後に第一句集「木の椅子」刊行。現代俳句女流賞や俳人協会新人賞を受賞と、輝かしい経歴
の持主であるが、仕事柄見事な生き方を示してくれた先輩諸氏に会うことが出来て、女が仕事をすること
や、女の生き方などを深く考察する機会にも恵まれ、それぞれの作品にもその時代時代の翳りや深さも加
わっていった。有名になったかのもんぺ姿になったのも、「生涯一女書生」として半分は出家したという
気持からの発心だったという。焦らず侮らず怠らずとも。
空を行く花びらで切れ、50代になろうとする気分を、散りゆく花びらの明るさと寂しさを素直に 詠んだ。 花石榴切火のごとし四十歳
- 石榴の花は万緑の中でとても印象深い朱色を散らすように咲く。王安石の「万緑叢中紅一点」
としての女性の有り様を男に伍して働く自分の姿に重ね見ているのだろうか。切火のようだと表現したの
は魔よけとして自ずから打つ火花の印象があったのだろう。
50代の花びらとの見たてと比べても、エネルギッシュなやる気まんまんの40代女性の姿が目に浮かぶ。
「休診の父と来てをり崩れ簗」「仕事休みたき日なり都鳥ま白」「小春日やりんりんと鳴る耳輪欲し」 「暗室の男のために秋刀魚焼く」「初老とは四十のをんな浮寝鳥」「蕎麦掻や涙もろきは父に似る」 「布染めて屋根にはじまる星月夜」「涅槃図の寺旅人を泊めにけり」「手花火も連絡船の荷のひとつ」 「磨崖佛おほむらさきを放ちけり」「青葉木菟なきやめばまた濤の音」 (第一句集「木の椅子」牧羊社昭和56年) - (H17年4月3日)松永 典子
谷川に冷して足と缶ビール
- 谷川の清冽な水が見える。缶ビールも足もいっしょくた、五臓六腑も人体という着ぐるみも何も
かも冷して、このきぃーんと美しい自然に同化し魂をも冷してしまおうという気持のいい句。足もビールも
という捉え方にそこはかとないユーモアが感じられる。
伝統的なものを批判していたが、写生もまた 虚構である事に気付き、滑稽ということを一段劣ったものと考えていてもっと人生にとって大切なこ とを詠まなければと肩肘張って悶々としていた学生時代があったからこそ、この滑稽やユーモアのよろし さに思い至ったのだと思われる。無駄な時間は無駄ではなく、絶対に必要なもののひとつだ。愛妻家にし て教育者。 悪人の往生したる涼しさよ
- 悪を行い、周りに鼻つまみものとして嫌われた者達にシンパシーを感じているのだろう。平気で
涼しさよと自分の立場をも明らかにしてちょっと偽悪を気取って悪びれない作者の粋を感じる。親鸞の歎異
抄がまた売れているらしいが、悪人正機説はなかなかに人間の深さを鋭く見つめて興味が尽きない。自分だ
けは正しいと思いこんでいる人が一番人を傷付けていたりもするもんだ。自分を悪人だとは思っていない
悪人に思いっきり、あんたが死んでせいせいしたわと言ってやりたい、よね。悪人として。
「美しきものにムリ・ムダ・ムラ・蛍」 「みどりの日美しうちのカミさんも」 「大雪や最後にひろう喉仏」
「学校に階段多し文化の日」 「ぼくたちの強気のように野菊咲く」 「愛妻家なれど冷奴を愛す」(「小西昭夫句集」平成22年4月創風社出版) - (H22年5月7日)松永 典子
朝寝せしこの世しんかんたりしかな
- 「俳句なんかに熱中していいことないよ。早くお嫁にいったら」
「お目障りですみません。誰か貰ってくれないかしら」
「少し手遅れだね」 など逢えばお互いに毒口がとぶ。そして私はこんな陽気な彼女に家に帰ってからの孤独の時間が待っている ことを考える。
―と。能村登四郎の一文からはじまる第二句集「花呪文」。柏の大地主の娘さんで、 この句集には両親の死をテーマにした句が胸を打つ。朝寝ができる身分ではあるが、しんかんたるこの世に たった一人目覚めなければいけない手厳しい現実がある。第一句集「新絹」より「新絹の白さ真夜には羽搏 かむ」の情感に変化はないが、俳句はどんなにか心の糧になっているか推測できる。 合掌の間にたくはへし朴の白
- 更に登四郎は言う。女は結婚して夫に仕え、子を生み子供の世話をしてその煤けた生活の中から
本当の俳句が生れると信じて疑わない私にとって、彼女の存在は全く異質である。―とも。
染色やお茶 、鼓と、いいご身分だね、まるで永遠に年をとらない「芦刈」のお遊さまじゃないかと追い打ちをかける。 が、俳句に対する傾倒は並々ならざるものがあり、彼女にとってはたぶんに信仰そのものだったのではないかと 思う。いつも華やかな装いで、亡くなるその日まで俳句を作っていたという。夭逝といってもいい年齢だった。 見事な人生だった。
「三椏の花しわしわと水殖ゆる」 「うつばりのごとくに塗られ父の畔」 「ふた親の野良着のしめり蛍 とぶ」
「時計指輪より身を抜いて熱帯夜」 「稲妻の匂ひに洗ふ箸と椀」 「いなびかり睡りて親の傍へゆく」
「生きものにあぶらののりし根雪の夜」 「ビール噴くはたとこの世の持時間」 「ただ帰る部屋をこの世にゐ のこづち」
「対馬くつきり風の間の野紺菊」 「朝鮮海峡指してのつるべ落しかな」 (「花呪文」昭和59年卯辰山文庫) - (H22年6月6日)松永 典子
明日海へゆく夕焼に泳ぐ真似
- 海へ連れてゆくと約束をすると、子は宿題も早めにかたづけ、おかずの匂いのする夕焼の中「あした
は海に行くんだ。」と誰へともなく話す。夕焼の海へ泳ぐ真似をしながら。
感覚だけに流されない確か な技術の冴えが感じられる。うまさを見せない本当のうまさとはこういうものだろう。だからこそ浮かび上が ってくる鮮烈なイメージ、江戸っ子の粋や伊達、シャレた感覚に時々ぞっとするような、闇の世界も寄り添う。 悪友に似て十薬の花点々
- 転勤の度にいろんな句会で勉強する機会を得た私には幸福なことに多大な影響を与えてくれた師が数人いる。この中の悪友といわれている久保田博と共にその最初の師である。
波郷門で十七年、波郷没後「沖」に初投句初巻頭と華々しい活躍で、25年目の第一句集「渚通り」は俳壇に衝撃的なデビューを飾る。
それだけに、すさまじい鍛錬だったようだ。序文 の能村登四郎は男の色気をいい、跋文の林翔はその後の活躍を暗示するかのような句群を取上げその無常観に触れている。そして、「基礎的な修業を経ないで、いきなり観念や心象の句に飛び込んだ人の中には、言葉の遊びだけの、比喩や、時には比喩のための比喩さえもみかけるが、さすがにこの人のは危なげがない。」と。
現在、俳人の節子夫人と共に立ち上げた「門」の主宰。いまだにバイブルである。
「白菖蒲剪ってしぶきの如き闇」「向日葵に煙のごとく老婆来る」「哲人のごとくぼろぼろ檻の鷹」「見得切りしまま枯兆す菊人形」「母わかき日の簪に似て椿」(渚通り)
- (H15年7月15日)松永 典子
田中裕明
ひらかずに傘持ち帰る花あやめ
- 10代の男子学生の句。見えないような細い雨が降っているのだろう。それでも傘をささずにあやめ を見ているが、やがてそのまま帰ってしまった。傘は買ったばかりだったのだろうか、それとも折り畳み の面倒な傘をひらかずにそのまま持ちかえったのか。あやめの、妖艶でいて折目正しき姿を年上の女性の 印象と重ねあわせてうっとりと見ていたに違いない。具象のなかに作者の心象風景が見えてくる。
濯ぎものたまりて山に毛蟲満つ
- 「青」に所属していた作者20代の記念に出した私家版。波多野爽波は、すでに大器の様相を呈して
いたこの作者の完成された作品群に注目していた。最年少にして、角川俳句賞受賞。平成12年主宰誌
「ゆう」を創刊、120名の指導にあたったが、昨年45歳の若さで死去。生き急いだ天才の死に俳壇の
ショックは大きかった。季語の本意と写生を軸に伝統詩としての俳句をめざしていた。
「紫雲英草まるく敷きつめ子が二人」「口の中ねばつく烏瓜ひとつ」「石積んでありおしろいに海の砂」 「滝落ちてずつと離れて濡れる石」「亀鳴くや男は無口なるべしと」「三伏の赤子の耳目かがやきぬ」 「柚子青くなる手拭の乾びをり」「昼花火続くや松の色さまざま」「宵闇や水打ちしあとぽつねんと」 「鳥の影急にふえたる添水かな」「鮎釣のどんどん川を下りけり」 (第一句集「山信」私家版昭和54年) - (H17年5月21日)松永 典子
都築智子
自らの重み負ふべし濃紫陽花
- あの手毬のような花の塊が案外細い茎に支えられている事に驚く。自らの重みとはその花の事だが 作者自身にも通じるものがある。最初の伴侶を早くに亡くされた後働きはじめ、3人の男の子を育てられた。 お子さん達がみな成人された後再婚されている。 もともと文学の素養があり「寒雷」で10年鍛錬された後、どんなにベテランでも会員から始まる厳しい「沖」へ。 句作22年後第一句集「花帽子」上梓。その12年後の平成6年第2句集「桜川」。
吾子とその選びし人と花火待つ
- やがて子に恋人ができて結婚するという。紹介されて間もない頃の甘酸っぱい複雑な心理で花火を
待っているのだ。これで息子も一人前。苦労が報われた嬉しさと、寂しさと・・。
幸せを絵に描いた様な 奥様から、突然働く母へ。そして再婚。と、激動の女の人生を送りながら、そんな不幸な影は微塵にも見えない ふわりとした華やかな存在感のある女性である。利発で勝気できらきらと自己主張できる女流の多い中で、 ごつごつがつがつしていないのは 彼女だけだったように思う。人に言われないと意地悪されている事さえ分からなかった私と、波長が合うのかも しれないと、なんとなく親近感を覚えていた先輩でもある。もっとも、彼女は何事もしなやかに受け入れる器の 大きさからくる余裕であって、私の場合は本物の間抜けだったという大きな違いはあるが。
「皮剥ぎの可愛い顔も糶られけり」 「菜の花は大地の生絹雨上がる」「痛さうな裸木に触れ棺出し」「りんりんと寒九の水に身を醒ます」 「箒目の乾きどんぐり出来不出来」「ブルネイの客泊まる夜のさくらんぼ」「添へ文の能筆にして蒸鰈」 「清明の天より届く鳥の羽」「波来れば波の高さに浮寝鳥」(句集「桜川」平成6年富士見書房) - (H19年4月3日)松永 典子
シャーベット掬ふみどりは森の風
- シャーベットを銀のスプーンで掬い上げ、まさに口に運ぼうとした瞬間の心はずむ気分が言い止められた。
メロンの色か、ミントの葉の色か。香りとともにそれはヨーロッパの森の風だというのだ。
渡欧の折の旅吟らしいが、特別気負わない作句態度に好感が持てる。旅に出るとやたらに、その地らしい
固有名詞を入れたくなって上滑りの報告に終わりがちであるが、どれも取って付けた様な無駄な措辞はなく、本当
の上手さを身に付けた人だと思う。作者はよく旅吟を発表して数々の佳句を物にしている。
あこや貝死ねば積み捨て花海桐
- 長崎の俳誌「棕梠」、「馬酔木」、「沖」と華々しい活躍をしながらも女子高の教壇を定年退職後、沖長崎を創刊
主宰した大先輩である。それのどれも平行して成果を上げているのは、驚嘆に値する。
とべらの花は、海岸 に自生し、白い小花の集まりが黄色に変わり芳香を放つ。大村や平戸では良質の真珠が採れ、鼈甲細工と共に有名。 とべらは公害にも強く見た目もいかにも強そうで花をとり巻く葉が玉を覆う貝に見立てられないこともない。
第一句集「朱蝋燭」は、得意の旅吟に加えて、長崎の風土を生活者の立場から深々と詠み上げたあこがれの句 集である。
祝婚歌島の高空桐咲けり
ごきぶりの振る髭ほどの真実か
弥撒にも出会ったことのある少女の頃がなつかしい。 (花弥撒)
- (H14年5月9日)松永 典子
中嶋秀子
あらゆる木あらゆる青実血を採らる
- 乳癌の疑ひありとの前書。どんなに不安な事だろう。その後乳房を取られて、無残な句が並んでいる。
あらゆる木あらゆる青実と切迫したリフレインにより不安な気持を包み隠さず表現。何の為に句を作るのか、
何の為に生きるのかとの自問が、すべての自然よと呼びかけながら過不足なく投げかけられている。表現者と
は心を裸にしてまで、書かねばならないのか。「白桃をいくつ食べても乳房なし。」へと続く。
昨日今日何ごともなく水を打つ
- 何事も無い苦しさもあるが、何事も無いありがたさもある。
人の世にある限りは苦しみと涙は つきもの。平穏な時は、その平穏さを有り難いとは思わないのに、人はたちまちにしてそうではない現実と向 かい合うことになる。その後の順調な回復もいろんな感懐と共に、命だけは残ったのだという安堵感と転移へ のどうしようもない不安感と共に、何事もなかったような日常へ戻る道筋を辿る。俳句の力はどのくらい作者 を支えたのか。いくらかでも回復の力になったのだと、同じ道を志す者として切に思いたい。
「寒雷」「沖」に拠り楸邨、登四郎に師事。「響」主宰。 (命かぎり)
- (H14年7月11日)松永 典子
潮風にはばたく日傘ひらきけり
- 若い女性のアンニュイも、何へとも無き不安も、この広い海に向えば何ほどの事かと思えてしまう。
海の清々しさへひらく日傘は鳥のように羽ばたいている。そこには、広大な未来があり、
どこへでも行けそうな気がするのだ。
学生からOLを経て結婚。子育てと、本当にうらやましい限りの充 実した時間を持ち得た。勿論、彼女の努力も半端じゃなかったと推察できるが、美しい女性の黄金時代の全 てを、佳句として第一句集「夏帽子」に綴じた。
- 粽解くにも弟の負けてゐず
- 大阪に赴任したばかりの彼女と、沖の仲間達で飲む機会があり、篠山へも行った。
お酒は弱いけれど、仲間と飲むのがとても楽しみですと。小柄ではあるけれど大物の風格もあった。
十数年前のことである。確か第二句集「窓」を上梓したばかりだったか。
師の清崎敏郎が、「母と子の 母の大きな夏帽子」と彼女の事を詠んだ。よき母であり、よき妻である事が出来たのも、俳句という心の世界 を持っていたからに違いない。その後、病気など負の部も多く味わい、持ち前の感覚とウィットに加えて深く 湛えられた陰翳と幅が出てきて、内面もますます充実してきているのではないだろうか。 (夏帽子)
- (H14年4月9日)松永 典子
我が足のこんなにでかい箱眼鏡
- 木箱にガラスをはめ込んで、水中を透視して魚を捕る道具。主に浅い所で用いる。覗かせてもらって、魚
ではなく自分の足の大きさに驚いたのである。たったこれだけで、違う世界を見るトキメキやら、慣れない事をす
る危うさに視点が定まらずうろうろしてしまっている大男(実際立派な体躯である)の姿等が瞬時に伝わってくる。
水の中では屈折率の関係で、尚更大きく見えたのだろう。このちょっとした視点のずれがおかしい。
逆説がふと湧くシャワー浴びてより
- ふと湧くで切れる。文学に関しては逆説も結構多い。逆もまた真なり。状況によって時代によって、時に
覆り定説になったりする。自分の信じている事や、進むべき道はこれで良かったのかとシャワーを浴びて思った。
あるいはもっと卑近な出来事だったか。人は思い込みをするものだ。時にまっすぐ進む頑固さも必要だが、一人の
人間が考える事はたかがしれている。異質なものを受け入れる柔軟さも、自分が間違っているのではと不安の念に
かられながら進む事も必要であろうか。リラックスした時のそういう思いつきや揺れ動く心こそが人を惹きつける
要素の一つなのかも知れない。
カリスマ的俳人だった父、故能村登四郎は師でもあり、その亡き後は結社 「沖」の主宰として、面倒を一手に引き受けている。
「子に土産なき秋の夜の肩車」と詠んだ父としての登四郎は不器用に愛情深い面を覗かせていたが、師として の登四郎は、研三氏には、他の若手より厳しくあたった。作句も自分から勧めたのではないという。それが本当の 父情というものだと今は痛いほど分る。第一句集「騎士」も句会に本格的に出句(定期的に)し出してから相当経って いた。
鋸のゆききを透かし夏氷
竹皮の脱ぎっぱなしへまたも脱ぐ
騎士といふ薔薇あり蜂を矢と放つ
どう見ても互角の若き竹二本 「騎士」等がある。 (鷹の木)
- (H14年5月17日)松永 典子
夏草の中の働く帽子かな
- 夏の草刈りは本当につらい重労働であるが、汗を拭いた後には充実感や達成感があり、生き ている実感と満足がある。これはそんな場面を見ていた作者が自然の中の生命力をやや羨望の眼差しで 捉えたのであろうか。働く帽子と表現した生命は、夏草に溺れそうになったり休んだりまた持ち直しつつ 確実に前進しているのだろう。人生の一齣に小さな人生を見る。
蚊柱に首の抜けなくなりにけり
- 蚊柱につかまったらなかなかぬけられない。払っても払っても寄ってくる。逃げようとすれ
ばするだけ顔中にぶつかってくる。首が抜けないという表現がうまい。しかも修辞に逃げ込んで、不適切な
引用や大袈裟な直喩の居心地の悪さを感じるような事もない。若い頃の、戦争という深いトラウマを持ち
ながらも乗り越えてきた母の世代の姿勢の良さが、若々しい詩心を保っているのだろうか。
「轍」同人。
「綿虫のどれにも焦点が合はぬ」「弟の死やつくねんと蕗のたう」「詰草のティアラ冠せて もらひけり」
「逃水が道を伸ばしてゆきにけり」 「夏掛のからまるアガサ・クリスティー」
「冬帝のつまみ上げたる如き富士」「不自由さうな雪吊の中の松」
「吹雪抜け人のかたちに戻りけり」 「考えてみたし栄螺の展開図」「さかしまにしても日の丸終戦日」
「霜柱土の匂ひを押し上げぬ」 「目づまりの急須囃せよ百千鳥」
「ペンギンに氷十貫原爆忌」「宅配の置いてゆきたる西日かな」「夢なら ば夜霧の娼婦にもなれる」(第2句集「草のティアラ」平成21年5月角川書店) - (H21年6月2日)松永 典子
変哲もなき三椏の若葉かな
- 中国名を結香、黄瑞香、打結花などという。7月ごろ新枝の先が三本に分かれて伸びるので三股 の名。ジンチョウゲ科 のガンピ、コウゾ等とともに、古来和紙の原料となった。うぶげに包まれた黄色い頭状花序が美しいので、 庭木としても珍重されている。花季が終わり若葉として万緑に加ると何の変哲も無くなった。という何気 ない句意だが、そのそっけなさがかえって 花の可憐さ、和紙になるという有益さ等を暗示させて、この何でもない若葉が、三椏なのだとの豊かな想い。 ジュズブサ、ヤナギ、ムスビギなどの方言名もあり、いかに生活に密着していたかがうかがい知れる。
梅雨に入る兎の巨き胃袋よ
- 兎は食欲性欲ともに強いと言われる。胃袋もそれなりに大きいのだろうか。いずれもペットとして
学校や家で飼育されているのだろう。欲望を押さえつけられた大きな胃袋が梅雨にむかって心細く、哀れだ。
単に兎といえば冬の季題になっているが、兎狩りの習慣や、食べ物の少ない冬に人里近隣で目撃され る事等、昔は自然の中にいた野兎が一般的だったが、時代と共にペットとしての兎の方が解りやすく、季感 もうすれつつある。野兎と区別して使用する人も多い。季語も世につれ・・である。
高校教師で、 「馬酔木」・「沖」の編集に携わり将来を嘱望されていたが、42歳で夭逝した。「九階草裾は千草にとりまかれ」 「還らざる旅は人にも草の絮」確実に来る死出の旅。たかが俳句、されど俳句である。(散木)
- (H15年6月5日)松永 典子
サーフィンのその頂点にみしは何
- 普段でもきっちりと和服を着こなしている見事な日本女性である。「沖」創刊と同時に能村登四朗の門に 入り、住居も近かったせいでいつも先生の周りにいて勉強していた。万事に控え目な先輩だった。そんな境涯の人 が若者が夢中になるサーフィンを夢のように見ていて、その頂点にいるときの感覚はどうなんだろうと思ったのだ。 すぐに波に崩れ落ちてしまうのに幾度も幾度も挑戦する姿を別世界の事として眩しく見ている。
飽食の児にはじめての麦こがし
- 大正生まれの良妻賢母を具現したような美しい女性はまた立姿も精神の姿勢も際立っていた。地域貢献に
役立つような知的な仕事もし、育児に俳句にと、どれ一つ手を抜くこともなくこなしていたという。20年以上結社で、
みっちり研鑽を積んでからの第一句集「雪代紬」はとても評判がよく、それに奢る事なく次の十年目に出た第2句
集「露芝」は珠玉の一冊となった。登四朗に「露芝に触れし足指いとほしむ」の句を賜った。
見事な俳句人生である。
「退くときも後はみせず涅槃潮」 「過去といふ浅く確な雛の傷」「枯いろを着て鴨撃ちの眼を惧る」 「口割らぬ大蛤の直火やき」
「みほとけに聖果を頒ちあやしまず」「やまと絵の霞の奥を知つてをり」「太葱の白さよ父情まぎれなし」 「更待のかたより易き蕎麦まくら」
(第二句集「露芝」平成5年8月卯辰山文庫) - (H23年5月8日)松永 典子
前髪を星に覆はれ夜を泳ぐ
- ため息の出そうな美少女だった。自分の美しさの価値を十分に分っていて、それでいて、
乾いた抒情によるナルシズムの昇華を試みている。この人ならと、誰もが認める舞台を自分で用意
した。
あまり人のいない海へ、誰かと行った。昼間の楽しい時間もさることながら、充たされ た気分とはうらはらな不思議な飢餓感や、得体の知れない何かに誘われる様に夜の闇に 一人抜け出し、ゆうゆうと泳いだ。満天の星。愛の女神アフロディテではなく、戦の神でもある月の 女神アルテミスのように。水仙になった少年のように。
滝を見る水晶体をたれも持ち
- 研ぎ澄まされた感覚と、べたべたしない抒情は彼女の作る作品のひとつひとつに輝きを与えている。句会に
は滅多に出なかった。類句や類想を嫌ったのだろう。かといって独りよがりではなく、
俳人の身内との電話代が嵩むと、なにかの折に聞いた。
作風はむしろその頃に、彗星のように現れた短歌の俵 万智に似て斬新だった。水晶体の発見は、この世の者とも思えない彼女自身の近寄りがたい無機質な美しさにも通じ ていて、滝の神秘性とも響きあっている。
母親、兄共に実力派の俳人で、ダンディーな兄正木浩一氏の夭逝は、彼女に大きな痛手となった。子供のいないのも相まって、いまだに生活臭のない大胆にして詩的(知的)な作品で、多くのファンを惹きつけ続けている。 (水晶体)
- (H14年5月29日)松永 典子
バスがきて一少年と虹が消ゆ
- バスがきてーーーの句はホントにごまんとある。この句は昭和50年代の句だから、今どき新しいな んていうのは句を読んできていない人であろう。古いフレーズがはいっていても、そこにその人らしさや、 捉え方の独自さや、発見があるとかの、工夫をこらした配合であれば何の問題もない。この場合、 バスを待っていた一人の少年が、来たバスに乗ったというだけの光景だが、虹が消えてしまったと捉えた。 見事な虹がそこに掛かっていて、反対側のバスを待っていた少年と思わず顔を見合わせた。 感動を共有した者同士のちょっとした気安さとるんるん気分だったのが、バスという現実が少年を連れ 去ってしまったので、またもとの自分一人に戻ったという軽い失望感。もしかしたら、虹はまだ残 っていたのかもしれないが、もう虹に見とれる気にはならなかったのだろう。一言も口を利いてはいな いのに、百年の知己のようだった。相棒や道連れなどとはこんな関係なのだ。
夏蓬ばりばり刈つて父葬る
- 父の死である。長けてしまった夏蓬、手強くしぶとい生命力の象徴としての雑草を、ばりばりと
やたらに意味もなく刈っているのである。父を亡くしてしまった男のくやしさが伝わってくるではないか。
第一句集「流藻晩夏」に次ぐ第二句集「早春望野」は、皆吉爽雨門からはじまって「雪解」同人、 「沖」同人を経て31年目での上梓。証券マンのかたわら坦々と作句活動を続け、今は悠々自適の俳句三昧 か。繊細な感覚の句が多い。
「天上は機織りてゐむ雪の鶴」「洗つても白魚洗つても生きて」「朧夜のどれも鋭き切絵の目」 「みつめなば母消ゆるべし白菖蒲」「木の実降りつぎ存問の隙もなし」 「旧師逝くそれかあらぬか長い梅雨」「詩齢にも七難のあり屁ひり虫」 (第二句集「早春望野」牧羊社)
- (H16年5月10日)松永 典子